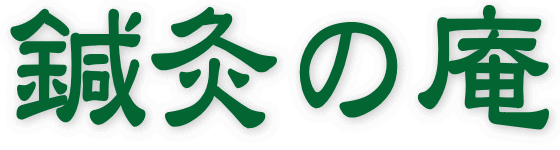鍼灸医術の門序
水、米、酒と書いたからとて三題話を始める訳でもなければ、日蓮の君子の造り方を云はんとするのでもない、世に水はH2Oであり、米は含水炭素であり、酒はアルコールとのみ考へてゐる人々に対していささか異論をさしはさもうとする下心からである。
水に硬水もあれば軟水もある、泉水もあれば流水もある、米に上品もあれば、下等もあり、内地米もあれば南京米もある。酒に灘の生一本もあれば合成酒もある。老酒もあれば新酒もある。
我々の実生活にはH2O含水炭素、アルコールよりも水、米、酒の方がぴつたり来る。
水、米、酒はそれ自体がある、どの水飯酒を飲んだり食つたりしても同じ事だなぞと語る手合いには話が通じない。
鍼や灸もその通りだ、鍼の味、灸の味の分からぬものに話しても初まらぬ。況や鍼や灸が機械的刺戟、温熱的刺戟療法だと片付けてゐる手合ひにはH2Oや含水炭素や薬局方のアルコールでも飲ませたり食はして置けばよい。話したつて分らぬ手合には話す張合がない、が、鍼や灸の味ひを知らんとする人は本書を見てもらいたい。そして、鍼を灸を施してもらいたい。
鍼行灸施は芸術だ、道楽心がなければ出来ない業だ、面白いではないか一本の鍼、一撮の艾で万病を治し得たならば、愉快ではないか鍼灸をして万薬の作用をおこさせるとしたなら。
相手は生きものだ、益々面白からう、又やりがいのある男子の仕事ではないか。
この門を通じて案内が分つたら、聖人のおわします、術の薀蓄の積まれてゐる堂奥に参じ、耆婆扁鵲の如き神医となる夢を見るのも又愉快ではないか。
この門が幸ひ前記の念願を満す道標となれば著者の望外の喜びである。敢えて蕪言を連ね序と為す所以である。
昭和廿三年戊子歳春分
後学 柳谷素霊
目次
第一節 緒言
第二節 醫・手当
第三節 穴
第四節 経絡
(一)経絡に沿ふて鍼灸の感覚が起る
(二)動物実験例
(三)X線による研究
第五節 気血営衛
(一)父母交媾成胎、先天之気
(二)児成り、後天の気
(三)営衛
第六節 三焦緒論
第七節 素質、外因、内因、不内外因
(一)素質
(二)外因
(三)内因
(四)不内外因
第八節 四診
(一)望診
第一図表 五行色体表
(二)聞診
(三)問診
(四)切診
イ、脉診
第二図表 六部定位、三部九候脉
第三図表 祖脉虚実脉
ロ、腹診
ハ、切視、経背
第九節 病証
(一)五運主病、六気為病
(二)正経自病
(三)五邪所傷
第四図表 五邪挙心為例
(四)臓腑病(井滎兪経合主治穴)
(五)十二経病(井滎兪経合補瀉穴)
(六)是動病、所生病と井滎兪経合原穴解
第五図表 井滎兪経合穴解
第六図表 井滎兪経合主治証
第十節 鍼灸治療方法の種々相
(一)鍼刺法の種々相
(二)施灸法の種々相
イ、打膿灸
ロ、焦灼灸
ハ、生薑灸、蒜灸、韮灸、杏仁灸
ニ、味噌灸
ホ、塩灸
ヘ、漆灸
ト、墨灸
チ、紅灸
リ、油灸
(三)病気に対する治療穴の種々相
(四)刺戟療法
(五)大久保適斎氏の鍼治論
(六)九鍼
第十一節 治穴配合の方則及臓腑取穴法
第七図表 五行要穴図
第八図表 十二原穴、要穴、郄穴、絡穴、兪穴表
第九図表 治穴配合の方則
第十図表 臓腑虚実補穴瀉穴表
(一)要穴解
イ、原穴
ロ、郄穴
ハ、絡穴
ニ、兪穴
ホ、募穴
ヘ、八会穴
ト、十五絡穴、交会穴、要穴
第十二節 鍼灸技術の稽古
(一)硬物通し
(二)浮物通し
(三)生物通し
(四)生体に於ける硬物通し
(五)生体に於ける浮物通し
(六)気の往来
(七)浮水六法
(八)灸の稽古
第十三節 補瀉の方法
(一)補の意味
(二)瀉の意味
第十一図表 鍼灸補瀉之表
第十四節 鍼灸科学の業蹟
(一)穴に関するもの
(二)鍼灸を刺戟とし、血液像に及ぼす作用に関するもの
第十五節 鍼灸科学化の方途
第十六節 結語
第一節 緒言
「鍼灸医術」は一本の鍼、一撮の艾による灸を人間に施して、その健康維持、疾病治療を目的とする医術であることは、おそらく本書を手にする人々の誰れでもが知つてのことであらう。
鍼灸といふても、針金であり、温熱火傷に過ぎない、これ以外に格別の道具立てや種や仕掛のあるわけではない。それだから「鍼を刺して、痛くありませんか、折れませんか、灸して熱くありませんか、痕がつきませんか、どうして、病気にキクのでせう」などと患者さんからハンコを押したやうな質問のあるのは、むしろ、当然なことなのだ。
考へてみればみるほど不思議なことだ、針金を体に刺して皮膚の上に火傷をさせて病気が癒るなんて、なんと不可思議なことではないか。
余は三十年来鍼灸治療をやつてゐるが、今もって不思議だとの思ひを去ることが出来ない、だから、素人の患者さんが不思議がるのは無理もない、不思議といふ意味内容は異つても不思議といふ言葉には変りはない、なんとしても不思議な治療法だ、と、鍼灸のことを思ふ。
しかし、世の中には鍼灸ばかりが不思議なのではない、不思議なことによつて、我々の身辺はとりまかれてさえゐると思はれる、それなのに、我々は不思議の念を起さないのは考へないからである、考へてみれば不思議なことが一杯である。
薬を飲んだり、つけたりして病気が治る、これも不思議なことである、けれど、これはそういふものだと考へ込ませられてゐるので不思議とさえ思はなくなつたまでである。
巧者な泥棒は釘一本でどんな錠前でもはづせるとか、あえて鍵がいらぬとかきく、これも我々からすれば不思議このうえもないことだ。が、彼氏からすればお茶のこさいさいである。なぜかといふに錠前の構造を知りこれをはづす技術が彼氏には出来るからである。
不思議といふ念には科学の芽ばえがほのぼのと立ちこめてゐる。学を学ぶもの、術を習ふものはこの念慮の場にときどき立ち還り自然のありのまゝの相を眺めるくせをつける心懸を持つべきだ。
自然はこうした高貴な精神の持主のみに悉皆財宝を包蔵する神秘の門をひらくであらう。
「鍼灸治療」欧米人ならずとも、これは確かに不思議なものだ。いざ、「鍼灸医術の門」を叩こうではないか、叩けよ、さらば開かれんである。
第二節 醫・手当
「鍼灸医術」は鍼艾といふ道具で病気を治す術といふことである。病気も不思議だが、これを醫する術は猶ほ不思議だ。
だいたい醫といふ文字が治療といふ意味なのだが、これは 匚 つまり箱の内に矢があり、殳はシュで戈のこと酉は酒で『内経』といふ漢方医学の原典にある醪醴のことである。
「酒は百薬の長」といふが、上古は治療に用ひたものである。
醫の上は矢とか、殳とかで、これは砭石及それに類した器具である。薬石効無しといふ言葉があるが、この石は古い鍼のことである。
醫は物理療法と薬物療法を示す語なのである。醫は癒であり、治療であり、手当てである。手当ては文字通り手当りであり、患難のところに自ら手が当るといふ自然作為から出た言葉だ。苦しむところ、痛むところ、痒いところになぜ手が行くか、教はらずして行き、理なくして行く自然行である。なでて気持よければ摩で、押へて気持よければ按である、強く圧へて気持よければ強め弱く圧へて気持よければ弱める、押へて気持のよいところは病気によつて異る。病気病気によつて最も気持のよい場所がある、これは感覚の問題だ。理屈の問題ではない、まつたく、天然所応に出たものである、医の原始的なものはこうして出発したものと私は思ふ。
第三節 穴
「鍼灸医術」は病気を治すものであり、治す為には無闇矢鱈に体のどこに刺してもよい訳ではない。無茶苦茶に鍼や灸して病気が癒ると考へたら、とんでもない考へ違ひだ。
もつとも、天然所応の場所としての穴を阿(アマネク)推して是(ヨキ)ところを捫(モミ)当(アテ)て、そこに鍼を刺し、灸を据える、所謂世上でいふ推し焼き、推し刺しで病気が治ることもある、それが反応点療法だ。けれど阿是穴のことを田の畦にたとへて畦穴ともいふて、上手に渡れば捷径として行けるが、下手すれば足を田んぼへ突込むぞとのいましめであるとうり、反応点にやりさいすればいつもキクとは限らない。いつも柳の下には泥鰌はゐないのと同じだ。キカないばかりか時には泥足になるやうに失敗して味噌をつけることさえある。
けれど、穴といふものはこうして人間に発見されたものだ、いはば古人先輩経験の所産である。
日本人なら誰でも柔道の語を知らぬものがない。柔術の当身とか活とかの言葉もしらぬもの少ない、よくいさかいをして人を撲り倒したり、撲り殺したりする、人はこれを当り所が悪かつたといふ、当たりどころといふのは、いはば、急所なのだ。柔道の当身なのだ。倒れれば気付けをする、今のは人工呼吸といふて胸郭運動をさせる為に、一人は患人の両手を引つ張り且つ屈する一人は肋骨下縁を押し上げ押下げる。呼吸運動をつけることによつて自動的呼吸を営ませようといふのだ。外からの運動によつて内の生機をうごかそうとするのだ。柔術ではこんな手廻りくどいことはしない、肩甲間部脊中腰に打撃を加へるとか、圧えるとかする。それで息を吹き返すものだが、それでも、息を吹き返さぬものは臍下丹田部をグツと拳で強圧する、それで、大抵は息を吹き返すものだ。こうしたことは、常識として誰でも知つてのことだ。倒す実験も、生かす実験も術に自信のある柔術家にとつてそれはそれこそ活殺自在に出来ることだ。生きた人間をそのまゝ実験に供することが出来る、全く事実のことなのである。
近世に於いて鍼灸臨床家の一人とし、声名をはせた澤田流開祖澤田健氏は実はこうした柔道から鍼灸の臨床に入つた人であつた。従つて実際治療に秀でてゐた。収斂によつて手にいれた「技術」をもつてゐた。
こうした人は澤田健氏のみではない、脈診一点張り、古法一点張りで九十才の長寿を完ふするまで臨床一本に生き通した八木下翁にしてもその通りである。熊本の鍼医 太田隣斉先生の事蹟を調べて見ても又然りである。実地から実地へ、実践から実践の行を積んで一家の見を樹てた。それは生体を生のまゝに、生活しつゝある生命全体として眺め、掴み得たからである。
穴は生命に直接するのであることは分つた、だから、生命の変異たる疾病に対して「処理の場」として使用し得るのである。
穴は人間が考へたり、工夫したりして作つたものではない。本能的にとさえいふほど自然に知らず知らずのうちに人間によつて、その存在を発見されたのである。西洋医学に云ふ、圧痛点、反応点、感覚投射像知覚過敏点(表在知覚点、深部知覚点)その他胃潰瘍に際しは現るゝ胸背圧痛点(dorsale Druckpunkt)盲腸炎に現はるゝMac-Burney氏圧点、ヘッド氏帯、小野寺氏圧点なども自然発生的なものだ。これ等は経験の所産である、生命全体の表現である。
これ等を連ね、組織を与え系統立てたのが、今われわれの手にある経穴なのである。
穴は阿是穴(天応穴、捫当穴)奇穴、私方穴、朝鮮穴、経穴と順を追ふて組み立てられた生命体の表現である。
註 詳細は別著「経絡治療講座」参照
第四節 経絡
病源の起るところは臓腑に本づき、臓腑の脉は手足に出で、手足三陰三陽の脉、腹背に循環して至らざるところがない、その流行不止、環の端無きが如しとのべてゐる、陽は天気に出で陰は地気に出る、天の気は降り陽経に沿ひ、地の気は升り陰経に沿ふと。
吾人生物は先天後天の気血をうけ、この気血が経絡を環周して止まず、終始流注し、生物をして生々活動の源泉を与へてゐるのだと説く、いはば、生命体をして生命体たらしめてゐるのは気血であり、この気血を循環せしめてゐるのが経絡だといふにある。
従つて、この経絡上にある穴を処置することによつて病気を処置することが出来ると考へたのである。
こういふ、考へ方から、穴は診断の場であると同時に治療の場であると云はれるわけである。穴はこうして、経絡の基盤に立つて、ここに無数にはりめぐらされた電線中におかれてある安全器の役割をもつとめてゐるのである。
手足にある三陰三陽の経絡の外に奇経八脉といふ経脉もある。だから、経絡といふと二十あることになる、『本草綱目』の奇経八脉考に「奇経八脉は十二正経に拘制されない、表裏の配合がないので、奇経といふのだ、正経は溝渠に比すれば奇経は湖沢のやうなものだ、正経の脉が隆盛となると奇経に溢れるのだ」とある。
それでは、このやうに謂はれてゐる経絡といふものは、現代医学的にみて何にあたるのだと聞かれては、返答に困まるのである。
現代医学的方法としては解剖して見るか、顕微鏡で見るか、レントゲン線で見るかしたら分るだらうと考へられる、が、事実は解剖してみても、我々が経絡だと指示したところには、皮膚組織、筋膜、筋肉、神経組織、血管組織、骨膜、骨組織、淋巴管、及体液を見るに過ぎない。顕微鏡でみても、これ等局所解剖学的、組織学的所見以外には何も掴むことは出来ない。レントゲン線で透視したのでは、それこそ何もなくなる、さようなものだつたら、無いのではないかと反駁されるかもしれぬ。
見ることの出来ないものは無いものだとは云えぬ。ものゝ存在は見ることが出来なくとも有得るものだ。視覚の範疇に入らないものは見ることが出来ない。が、香ぐことが出来、聞くことが出来、味ふこと出来、感ずることが出来る。それ等は一つの存在形式を示すものだ、夢は掴むことも握ることもできないが、まさに見ることは出来る。我々の感覚ではどうしたつて太陽は東から昇り、西に没する所謂天動説を信じない訳には行かないが、理性は地球が動くのだといふ、このやうに物の存在と真実はそれぞれのありやうを持つものである。
経絡もそうなのである、見ることは出来なくとも存在することは確かなのである、我々は経絡に立つて、その存在を前提として臨床上に効果をあげてゐる、そればかりではない次の二三例の実験は経絡の存在を示すものでさえある。
(一)経絡に沿ふて鍼灸の感覚が起る―これが其の一である。崑崙穴(足外踝の後方)に鍼灸して、足の太陽膀胱経といふ、頭、項、肩、背、腰、尻、大腿、下腿後側、足部に貫通してゐるいわれる経絡に、電気的なピリピリとかズンズンといふ響がつたわる。
丘墟穴(足の外踝の前際の陥凹部)に鍼して、足の少陽胆経といふ、外眦、頭角、頚、肩前、腋、体の外側、大腿外側、下腿外側、足背第四趾に循行してゐる経に沿ふてズンズンと響くのである。
このやうな感覚は鍼し灸されるものに、まさしく、存在するのである。暗示ではない、自然発生的に患者の方から、そういふのである。このやうな、在りかたもやはり存在には相違ない。感覚の上に於いて存在するのである。このやうな在り方を神経伝導学説で説明できないものか、と、実は真摯な医学者がやつてはゐる、が、まだ明瞭に組織立てられる段階にはなつてゐないやうだ、つまり、科学化されてはゐない、が、事実このやうな感覚が生起するかせぬかといふ実験は、なんでもないことである。丘墟穴なり崑崙穴なりに鍼を刺しさえすればよいのである。(但し、個人差、技術差が条件となることを忘れてはならぬ)
(二)動物実験の例―兎の頭の毛をそつて、真中に灸を据えた、灸の刺戟の為に毛根が刺戟されて発毛することは常識でも考へられる。且つ、灸刺戟の周囲から発毛しそうなものだが、事実は案に相違して縦列に発毛したといふ例が鍼灸学界に発表されたことがある。兎の督脈に施灸した実験である。動物には動物の経絡がある。原典とも見るべきものは中国版『療馬大全』であらう。動物による経絡の研究には最も必要な文献だと思ふ。
(三)X線による研究―バリウムを空腹時に飲ませ、X線写真を撮る、足の三里穴(胃経)に刺灸して後又写真を撮る、施鍼灸前と後とを比較する、次に他経に鍼灸して、同様写真にし、これ等を比較して、経絡の存否を決定出来る、これは直接人間を生活体のまゝに研究出来る最もよい方法だ。我々はこれを「動態基礎医学的研究」という。
この他体液の分泌、臓器のはたらき等について鍼灸施行前後の比較が実験的に出来る訳である。此際、経絡刺戟と経絡外刺戟との比較研究も是非せねばならぬことである。
殊に、柔道に於いて前記せる如く、胆経上の臨泣穴、地五会穴(柔道の草がくれ)に打撃を与へて胆の障碍を起し、肝脾腎三陰の経の交るところの三陰交に打撃を与えて、肝脾腎の障碍を起す等の事実は実験することにより新しい知見が出ることであらう。
このやうにして経絡の存否を生体実験的に証明できるだらうし、ここに、科学化の鍵がある。このやうな方法に於いて、生体実験真実なる相に於いて経絡の存在が明白となるならば、現代医学に新しい素材を提供し、これをして、一歩前進せしめる踏石となるであらう。
第五節 気血営衛
経絡の表明は一応感覚の面に於いて処理されるかに見える、それでは、その経絡をめぐる気血はどう説明されてゐるか、一応の当りをつけて置く必要がある。
男女の交接は自然発生的であり太古素朴の人には不思議とも思はなかたつた、が、子供が産れるといふのは不思議なことだ、と我々の祖先は考へたに違ひない。この考へは当時の「科学する心」であつたらう、今でも男精泄出を「気」が行くといふ、こうした、男女交接の相を他生物と比較し、そこに類型を求め、古代人的な一つの説明―即ち彼等の科学―が次の考へなのだ。
(一)父母交媾成胎、先天の気
父母交接の間父の一滴の精液、母の子宮に凝り、胎を致すものだとす、交接の間、女子の感気専にして子宮の門戸開発の時、男の陰深く至つて直ちに子宮中に射せば男の精気よく子宮に納り女精と合して胎を生ずるのだと云う、『内経』の「天年篇」にも「岐伯曰以母為基、以父為楯」といふも同じである。
男女両精子宮に入れば子門閉塞し再び開かない、女子の経水止まり、精胎養ふ、男女の象形を生する象形の生長につれ子宮も張脹する、これより先、胎上浮皮を生ずる如く、胎気始に生ずるものを胞衣といふ、胞衣は胎児母腹にあるや一系を出して臍に連る、それが、臍帯である。母の水穀血液濁れるを胎衣に、其精の精気は臍帯を伝ふて胎を養ふのだとする。
双胎は子宮開くこと再度、男精納ること再度なるに生ずるものとする、男精は厚く少く、女精は薄く多い、一交接の間女は両三度泄精するも、男は一度をもつて期とする、それは猫など異性の異るによりて毛並みの異つた子を産むことなどから気づいたことではあるまいか。
父母会交泄精の時、父の交感の一気、其の精中に存する、それが其の子の神となると説く。性質の遺伝と見ることが出来る。父精中に存するを神といふ、精はもと陰であり、下りて下焦陰位(腎)に留まり、神は陽で上り上焦陽位(心)に当る、精の生を致すは神による、神の生を致すは精に舎りて能気あるによるといふ、だから、神精両者は生命の根であると説く。個性である。
ここで、先天の神精があることを知る。それは父より稟るもので、清浄粹明なもの、清中の清である、腎は水蔵であるが、陽気を有してゐる。この陽気が先天の元気である。これは難経八難にある「諸十二経脉者共皆生気の原に係る」といふ、生気の原である。これは又、十二難の根本、腎間の動気、五臓六腑の本、呼吸の門、三焦の原、守邪の神、命門の火とも称する・腎中の相火ともいふ、精の用である、神は火の始め、火は神の根、天授の神気、人神なりといふふうに思想が発展した。これは心神日(君火)とは別なるものとされた、心は心臓に舎り、心の主が神である。その位は膻中であるとする。
子宮中の両精合して一ヶ月は白露の如く、二月は桃花の如く、三ヶ月にして始めて胎形を芽し、漸次生を成すと説く、十月臨産をは自然の理にして十は数の極なれば普通とするが、八九月―十一二月と実際は生産に遅速がある。これ等を古代人は、草木の果実、時期、質の剛柔により熟するに早遅あるが如く、父精母血の虚実、天気自然の状態によつて異ると考へた。
育胎中女の経水止るは人の知るところである。経水は経脉(任脉、督脉、衝脉)が子宮胞中に起り、会陰に行く、従つて、子宮は周身の諸経の血液尽く是に注ぎ遂に陰戸に下り泄れる、これが経水だとする、この経水が育胎の為めに外泄せず、為に、孕婦は経水を見ないのだとした。然し、孕育十月の中に経水の下るものがある。併も、其胎の患なきものは其婦の天稟、血分有餘の質であるから、精胎を養ふ外、なほ泄す所の餘血があるからだと考へた。このやうに、自然認識的に考へたものであつた。こゝにも個体差を物語つている。
さて、婦人生産し終れば乳汁通ずる、女の乳房は上部に露はれて、乳液上に溢れるは、泄精が溢れて上るものだとした。従つて、乳汁泄通の間は必ず経水下らぬものと考へた。上に通ずる乳汁と下に泄るゝ経水は倶に血液の化せるもの、中焦水穀の精微になるもので、注ぐ所の部属に従つて赤く(経水)白(乳汁)いのであるとした。産後乳汁少き者は中焦のはたらき少きか、水穀精微虚するか、任督衝脉に渋滞があるかである。
(二)児成る、後天之気
以上のやうにして、児は乳哺水穀の精気を受ける、それが後天の気である。これを受け、情志起り発し、喜怒志憂驚恐の情起り、色欲泄精の気が備はる、清中の濁気ある為めとする。
このやうに成る先天の気、後天の気が所謂気であるが、胎中に於いて既に気はめぐつてゐる。形体次第に具る、精神を養ふ者なきときは絶す、神より気わかれ、精より血わかる、気血は精神を行らし養ふ、気は神の中より別れ、血は精の中より別れ出る。
気は周身に満て温なる者、形気なり、肺に属し舎る、血は一身に満ちて潤ふ者、肝に蔵る、陰精より別るゝものなるも赤色陽色なるは全く陰に属するものではない。その用は陽に応ずるを示す。血は昼夜周身を運行すること十六丈二尺の経脉に従ひ、五十度にして流行する。
精神は根で気血は支である、然るに、気血を舎す肺(気)肝(血)が根本たる精神を舎す心(神)腎(精)より上に位す、脾は穀府で四方に及ぶ、これは草木の根は下に、支葉は上にあるのと同じだとみた、人身万物倶に形は気(天一水)より生じ形なりて後気(地二火)形を養ふ。
穀府たる牌のはたらきによつて飲食物は中焦(脾胃)に入り穀の精微は上つて陽分に行き(蒸れ気分に行き)神を助ける、陰分に行くものは下つて血分に注ぎ精を助ける。これによつて、皮肉筋骨毛髪頭足養はる、と考へられてゐる。
水穀胃中に入り、先づ蒸出する気升りて膻中に会聚し、呼吸を致し、肺気を助け、心神を養ふの気となる、これを宗気といふ、宗気の聚る所を「気海」といふ、この「気海」は膻中の所にて胸内であり、下焦臍下の「気海」は陰中の陽気の聚る所である。
乳哺水穀胃に納りて脾これを消化し、水穀消化の精気は変化して営血となり、其の悍気は変化して衛気となる、精気と悍気により気血養はれ、精神又これにより養はる。
このやうに、気血が全身を養ふものと考へられたのである。体液に疎き現代医学の考ふべきところであらう。
(三)営衛
難経三十難に「人は気を穀に受く、穀胃に入つて五臓六腑に伝ふ、五臓六腑皆気を得て、其の清なるを栄と為し、濁れるものを衛と為す。栄は脉中を行き、衛は脉外を行く」といふ。
栄は陰であり水穀の精気、其行は遅く、清者は滑利濁中の清者也、衛に従ひ中を行ぐ、衛は陽であり、水穀の悍気其行は速く、濁者は慓悼清中濁者也、外を行くものである。
然し、精気が脉中に入れぱ濁り、悍気が脉外に行つては清む、栄衛は皆水穀の気であるが、別けて云ふと、栄を血とし、衛を気とするのだといふ。これ衛を淋巴液、栄を血液といふ所以であり、これ等を気でいふと元気、正気といふが、正気虚せぱ邪入るなどといふことは淋巴球、白血球など血液、血清中の抵抗物質のはたらきと考合して分るやうな気がする。
衛気は脉外を行き、営(栄)気は脉中を行くことについて明治薬学専門学校長たりし恩田重信氏が七十七才の著「漢法医薬全書」二三五頁に次の如く記載してゐる。蛋自質、脂肪、含水炭素の三つは必要欠くべからざる営養素と唱えてゐるが蛋白質でも、合水炭素でも、固休又は液体では何んの役に立たぬものであり、どんな多量に営養物を含んだ飲食品でも胃腸に入つた営養素が奇麗に水に溶解しなければ三文の価値もない。所で水に溶解するといふことは取りも直さず営養素がガス体に変化するといふことである。食塩はよく水に溶解するが普通一般の人は其の食塩が水素ガスの様なガス体に変ずるとは思ひなさぬのである。が、実験に拠れば水に溶けた食塩はガス体の理学的性質を立派に具備してゐるのである。言ひかゆれぱ、飲食品の営養素は総べて気体となつて吾々の全身に瀰満してゐるのである。是れが即ち素問霊枢の謂ふ気なのである。然もこの気に伴ふて全身に循環してゐるのが血液である と書かれてゐる。恩田氏は余の餓灸治療を受けた人であるが、談話中「脉外をガス体が行り、脉中の血液がこれに伴ふて行くのだ、それは西洋人で既に云ふた人がある」と語られてゐたが、餓灸術はかゝる気血経絡を対象とする治術であり、かゝる、人体生成の理に基ける治術なのである。
そして、これ等の事柄はなほ一層科学的解明を与へらるゝ時機が到来するであらう。けれど、我々は「疾病を治する為めの鍼灸術」こそが唯一無二の目的であるから、これ等の知見は先哲の臨床的遺言として、一応はこれを前提とし、先哲の実証医術に至る手振りを習ひ手に入るべく精進せねぱならぬ。
第六節 三焦諸論
三焦は漢方医学に於て難解なものゝ一つである。三焦とは何物か、それについて、先人達は色々とその解釈に苦労した。
難経三十八難に「三焦は原気の別使、諸気を主持し、名有りて形無し其経手少陽に属し、外府といふ」とあり、三十一難に「三焦は水穀の道路、気の終始する処」とある。
そして、上焦は心下の下鬲、胃の上ロにあつて、内れて出さざるを主り、霧の如く、五穀の気を化す。
中焦は胃の中脘上らず、下らず、水穀を腐熟し、津液を蒸し、漚の如く、精微を化し、肺に注いで化して血と為り、生身を奉養す。
下焦は膀胱の上ロにあつて、漬の如く清濁を分別し出して内れず、表裏の水を通じ、汗と尿とを瀉す。
とある。これだけでは、何んのことかわけが分らないのは、さもあるべきことである。
(一)素問霊蘭秘典論には三焦は決瀆の官、水道これより出づとあり。
(二)中蔵経には三焦は人の三元の気なり、五臓六腑、営衛経絡、内外左右上下の気を総領す、三焦通ぜば内外左右上下皆通ず、身に周りて体に灌ぎ、内を和して外を調へ、左を栄し右を養ひ、上を導びき下に宣ぶるに於て此より大なるはなし、三焦共に気治るときは脉絡通じて水道を利す、惟だ三焦独り大にして、諸蔵与に匹敵無し、故に名づけて是を孤之府といふ」といふ。
その後、唐容川氏(現存、中国人)は「三焦は人身上下相連の網膜膏油なり」と云ひ、我国でも石坂宗哲は「医源」に三焦の二字古へ![]() の一字に作る、
の一字に作る、![]() は臓なり、其象常の大さの如し、脾に属して、胃下に横る」といひ、三谷公器は「解体発蒙」で「上焦は胸管・中焦は膵臓、下焦は乳糜管なり」とす、寺島良安は「和漢三才図会」に「三焦は上焦中焦下焦の謂なり、焦は火の類に象る、色赤く陽に属するの謂なり、腔腹の周囲上下全体に於て大嚢のごときものなり」といひ、石戸谷氏は「三焦は内分泌系統なり」と、久米嵓氏は 上焦は肋膜、中焦は横隔膜、下焦は腹膜なり」といふてゐる。或は交感神経系統に於ける上神経節、大陽叢、下腹叢といふ説もあり、和名では「美乃和太」ともいふ。
は臓なり、其象常の大さの如し、脾に属して、胃下に横る」といひ、三谷公器は「解体発蒙」で「上焦は胸管・中焦は膵臓、下焦は乳糜管なり」とす、寺島良安は「和漢三才図会」に「三焦は上焦中焦下焦の謂なり、焦は火の類に象る、色赤く陽に属するの謂なり、腔腹の周囲上下全体に於て大嚢のごときものなり」といひ、石戸谷氏は「三焦は内分泌系統なり」と、久米嵓氏は 上焦は肋膜、中焦は横隔膜、下焦は腹膜なり」といふてゐる。或は交感神経系統に於ける上神経節、大陽叢、下腹叢といふ説もあり、和名では「美乃和太」ともいふ。
かやうに、種々な説があるが、じつくりとこれ等の説を眺め、且つ臨床からこれを検討したらどうなるか。
霧の如く、漚(オウ)の如く、漬の如しといふは用の面を言ふのであるし、難経の「無形有名」とみることが出来る、決瀆(水をはき出す溝)同様である。網膜膏油然りである、和名美乃和太も同じである。焦といふ字解からはたらきを示すと見ることが出来る、上焦肋膜、中焦横隔膜、下焦腹膜はその部処に於けるはたらきとも考へられる。又石坂宗哲の![]() は臓なり膵なりとするもその作用と見るがよい。
は臓なり膵なりとするもその作用と見るがよい。
ともあれ、三焦は鮭のメフン(血わた)の如く即ち美乃和太であり、ホルモンであり、エネルギーであり、従つて熱であり、水穀精微をして力(酸素)ならしめるものであり、下焦に於いては精ホルモン(腎精)であり、と理解されてよいと思ふ、こう見れぱ原気の別使ということも分り、「無形有名」ともなり、更に「気の終始するところ」とも分るわけである。全身に存在して各々をして、連絡発生せしむるはたらきあることも、全身の大嚢であることも分る思ふ。焦は火であり、エネルギーであり、熱であることは分つた。これが、生体の原気と見るは何んの差支えもないではないが、たとへ、形あるものとしても、一定の形なきものであるから、「無形」のものであつて差支えない、然も各細胞の膜及液のはたらきとなりて全身の各所にあつてそれぞれの活力となれば心臓より出る血に比しての別使とみるのがあたりまへである。然もその代表的なもの、然も最も焦のはたらきのあらわれてゐるものを三つの焦のある部分と見るに何んの差支えがなからう。
こういふことは全体綜合的に人間をありのまゝに眺めるとき、全一としての相関関係からながめ、細胞個々の生活とその環境について考へるとき、そこに、はたらくものとして三焦を考へることは理の当然である。これを三焦経に連関せしめ、「外府」とし、大にして全身を被包し、部分に於いて各細胞間の連絡をはかるより「孤之府」とみるも又当然、それ等の間の新陳代謝の作用なす為に入れ且つ出すは、まさに、「府」であり、「焦」である。
これ又、古典の原典批判によつて、新しい科学によつて、やがてその真相がつかめる時代が来るであらう。
とにかく、我々はかゝる作用を為すものを想定せる古人の経験力におどろくものである。
原気をつけるに、これ等生機の源たる三焦の示現する、三焦経、膻中、中脘、開元の諸穴をよく澤田健氏等が使ふのは理由なきわけではない。
先天に於いて、先天の気は父母の気に於いて虚実があるべく、後天に於いて飲食精微の如何は気血をして虚実せしめ、原気これが為に強弱を生じ、従つて原気の別使たる三焦これが為に作用に盛衰を示し、身体これが為に消長を示すは理の当然である。これを治する、君火に直接せず、相火たる三焦をねらうは、何んと治療学的に妙手なりと考へぬわけには行かぬではあるまいか。
第七節 素質、外因、内因、不内外因
人間は前節に於いて述べて来たやうな「生活のしかた」と見るのが漢方の人間観である。
このやうな、生機で生々と発展し、生命の拡充をつづけれぱ病気にはならぬ、が、この統紀を紊すものは病因であり、病邪である。
これを、古人は次の如く見る。
(一)素質―先天的素質と後天的素質に区別する、先天的素質原気の強弱であり父母より亨けた気に基づく、遺伝的なものである、後天的素質は天候、風土、生活環境等によつて生後得たるもので、気質を左右するものである。内的のものと外的のものがあるのはいふまでもない。
近年、体質、素質、体型等の学問が若々と西洋医学にはじめられてゐる。血液型O・A・B・ABなどはメンデルの法則により一生変らないものとされてゐる。判定の材料は血液ばかりではない。唾液、汗、涙、乳汁、体液、分泌液、更に腎臓ゃ肝臓等の臓器細胞によつても分るとされてゐる。これは「血清学的な体質、個性の見わけ」と考へることが出来る、血液ばかりでないところに漢方医学的なものと似たものを示してゐる。
気質と血液型との関係を古川氏は次のやうに述べてゐ。
O型は自信強く、理智的であるが、強情で融和性に乏しい。
A型は温厚で従順である、同情心が強いが、心配性で決断力が乏しい。
B型は淡白で快活で社交的ではあるが、移り気で意志薄弱である。
AB型はA型とB型と合つた気質をもつてゐる。
このやうに西洋医学的にも素質といふことを問題にしてゐる。
更に「体型学」からすれば「ずんぐり型」即ち、肥満、面赤、短頚、広胸、多血、体格佳良なもの、俗に「卒中質体質」のものと、「すんなり型」長身、長頚、筋肉がやせ、皮下脂肪が少い、顔面蒼白、眼光鋭く、事に敏で、俗に「肺癆体質」といわれるものである。この他に「アトニー性体質」「粘液性体質」等々がある。これ等は漢方医学に於いて陰陽五行臓腑に於いて区別するところである。
これ等の素質は内外の環境に立つて、或る病に対し発病し易きか、し難きかを示す一つの疾病構成要素となるばかりでなく、原気(自然癒能力)の強さを示すものと思はれる。
医学博士渡邊三郎氏が「治療方面より見たる内臓反射」の第一章に「周知の如く生物の生活は其の生体と共の周囲との関係で成立つてゐる。生体は絶えず其の周囲から無数の而も多種多様な影響を被むる、生体に斯く影響を及ぼす総べてのものは刺戟であつて、夫れは先づ生体の環境の諸条件の変化で惹起される、生体に刺戟感受性が存在する場合は其の刺戟の刺戟作用が発揮される訳である。即ちそれによつて、生休の内に又は外に向つて機械的又は化学的の変動が起きる。上述の如く、生体が刺戟の刺戟作用に対して能動的に作業を営み、之に応答する、之れが即ち反応である。
外囲の諸種の物理的、化学的或は生物学的「エネルギー」の変移は常に生体に刺戟を致し、生体は之に反応して、新に生休内に諸条件の変化を起し、之れは亦夫れに刺戟作用を発挿して、反応は次から次へ進む、之れが生活の表現であり、生命である。
かゝる刺戟と反応の関係はそれが健常生活であらうと、病的生活であらうと同様であつて臨床なる立場からすれぱ、反応を離れて生体を考へる事が出来ず、従つて治療学に於ても『刺戟と反応』とは全くその根本的基礎観念である。」
と述べられてあるが、刺戟に封する反態性は多分に素質即ち個人差があることを認めねぱならず、元気なる概念で示さるゝものが如何に重要な役割を演ぜねぱならぬかは、分明なことであらう。渡邊博士は更に語を進めて、「かく外より内の影響は内に入つては内と内との相互影響となり、次に内より外への表現となる、而して、かゝる生活現象の根幹を為すものは、実に生体の植物性機能である」と結んでゐる。
漢方医学に於ける元気の別使たる三焦のはたらきと比較してみ、且つ、元気が唯一の素質を為すとする漢方の表現と比較しみるならば興味深きものがあるではないか。
生命を漢方医学的にみれぱ「生気の原であり」「守邪の神」である、これを医学的にみれば「人格の表現」であり、これが「生体反応」の原である。即ち、素質に内含される一「エネルギー」である。この強弱が外邪内傷を受ける度合を示すものと思ふ。
(二)外因―外邪ともいふ、風、塞、暑、湿を普通いふ、四気外感の気である。風は百病の長であり、寒は天地殺属の気であり、暑気は火邪であり、手足熱し、燥渇し、大便痞硬せしめる、湿邪は腫れ重る。
中風は風邪で肝を傷り、傷暑は火邪であり心を傷る、傷寒は寒邪で肺を傷る、中湿は水邪(霧雨蒸気の類)で腎を傷るのである。
これ等の外邪は内正気(原気―生命力)の虚なるによつて生ずるものとされてゐる。
(三)内因―七情内傷ともいふ、喜怒憂思悲恐驚で、内から五臓を犯し、正気をして衰虚せしめる因であると考へられた。
古典は説く、五蔵に五志がある、五志七情は神気の発動に出る、これは五蔵各々其の志を分主せしめてゐるといふ。現代科学の「発達心理学」と比較すべき言葉である。
肝(怒)心(喜)脾(思)肺(憂)腎(恐)は各々そのカツコ内を主る。
〇肝木は春に応じ、発生勇猛の気(将軍の官)人怒る時、気逆し、息数はげしく、眼張り、怒り極つて面青くなるのである。
〇心火は夏に応じ、散じて開き、人の喜ぶや気開きて散ずるに生ずるのである。
〇脾土は土用に応じ、中宮に在つて、四方に応じ、人の思は四方の事を聚めて抱くに生ずる。
〇肺金は秋に応じ、収斂粛殺の気で、人の憂ふるや、其気収斂するものである。
〇腎水は冬に応じ、水よく順下して卑きに降る、人の恐るや其の気、陥る、恐は腎の志なり。
以上の如く五志の総べて属るところは一の神気である。五志七情は五蔵五行の気象に応じて各々分主ありと雖もこれを総括するものは神気であるとする。
怒は共の神気の激より発して、共の標は肝木逆上猛桿の勢に及べるものである。
喜は共の本榊気の緩より発して其の標は心火開散の勢に及べるものであり。
憂は共の本神気の収るより発して、其の標は肺金収斂の気に及ぶものであつて、悲も同じ。
恐は其の本神気の陥より発して其の標は腎水の下りて昇らざるに及ぶもので驚も又同じである。
思は其の本神気の結ばるゝより発して其の標は四方に寄り応ずる及ぷものである。
とされてゐる。五志七情の太過より病む者その主る蔵の位のみを治するばかりでなく、共の志の及ぶ所の蔵位を治せばならぬと説いてゐる。
かやうなる、表現で漢方医学は説いてゐるが、七情の肉体に及ぼす作用は軽々に看過し去ることは出来ない。心内にあれば外色にあらはるといふことは誰れでも知つてる通りであり、物思ふは一夜のうちに白髪となるとか、心配事は食事を減ずるとか、突然の喜び又は恐怖は心臓の鼓動を早め、物の好悪は味覚によるが、病気になれぱ余計好悪を感ずるものである。
キヤノンが怒らせることによつて副腎ホルモンを増加すると実験的に証明してゐる。この例は感情と肉体との相関々係を示すものである。更に注目すべきはアドレナリンの作用である。即ち①心臓の機能を亢め、血管を収縮せしめ、血圧を高める、血糖を増加させる。これは肝木の作用が、その子たる心火の作用に影響を与へることを示し、②気管枝筋肉を弛緩させることは肺金に影響を与へることを示すものである。このことは後段に於いて問題とするところである。
現代医学的に見るとき、これ等の脳皮質の観念から植物神経の高等中枢に作用して、そこに一定の気分が成立し、迷走神経或は交感神経を介して末梢効果器官に機能変化を来すによると解釈されてゐる。即ち精神植物性反射といふのであるとされてゐる。
これ等の知見は現代科学者の研究になるものであるが、直観的漢方医学といはれる如上の思想が漸次解釈される日があるであらう。
(四)不内外因―身体労倦、過房等である。
以上は古典的病因であるが、元来、陰陽府蔵経絡の気が虚実相等しきを正となす、偏虚、偏実は其の正を失ふのである。是れが為に邪の侵すところと為す、偏実は内邪を得て病み、偏虚は外邪の入るところとなりて病生ずるのである。要は原気(正気、素質、体質)の盛衰如何にあるのである。銀灸の最終始の目標は結局正気なのである。
第八節 四診―望(神)、聞(聖)、問(エ)、切(巧)
四診とは望、聞、問、切をいふ。漢方の診察法は物心両面を一如と受取り、修練せる直観にてその病情を把握せんとするにある、自然のまゝの相を経験的に累積した知識をもつて彼我一体の境地に立つて把握せんとするにある。
こゝに正確なるを直観力を作る為に修業を唯一の手段としたことは先哲のきびしき求道心、はげしき修練に見ることが出来る。
亀井南冥が「医は意なり意といふものを会得せよ、手にもとられず、書にもかゝれず」「論説をやめて病者を師とたのみ、夜に日を継いでエ夫鍛錬」と云ふも皆修業の方法を示すものであり、和田東郭が「古人の病を診するや、色を望むに目を以つてせず、声を聴くに耳を以つてせず、夫れ唯耳目を以つてせず、故によく病応を大表に察す、古人の病を診するや、彼を視るに彼を以つてせず、乃ち彼を以つて我となす、共れ既に彼我の分なし、是を以つて能く病の情に通ず」と至言である。
望診は望んで、聞診は音声を聞いて、問診は病者の言ふところを聞いて、切診は触診によつて病情を知るのであるが、どれも、これも、練磨せる直観力によつたのであつた。分析を総合しての判断ではなく、古典の特徴である全体をそのまゝ把握せんとする態度である。この為にはたゆまざる精進がいるのである。古先哲はこれをやリ途げたのであつた。
(一)望診
澤田健氏は望診に秀ひでてゐた。澤田流の門下、代田文誌氏の筆をかりよう。
「全く現代医学の常識では解り得ない事をやつてゐる、患者が治療室に入つて来ると、貴方は幾時頃から熱が出てゐるとか、それから貴方は何処が悪るいとか、坐らぬ先から言ひ当てる、先生は症候も聞かずドンドン治療をやる、さうしてドンドン成績が挙つて行く、毎日々々治療室を見て参りますと私達が想像もしなかつた病気がドンドンと治つて行く、かくして鍼灸医学の優秀なることを実験的に知つたのであります。事実優れたものだと云ふことを、この時始めて知つたのであります。先生は斯様に自由自在に治療して行くのでありますが、其のやり方は只古典のまゝをやつて居るに過ぎない、自分一個の考へでやつて居るものではない、古典のまゝに治療するのみであります」と述べてゐるが、全く余も故澤田健氏には何辺も会つてゐるが、その望診は素晴しいものであり、只驚歎するぱかりであつた。然しながら、この道は先哲の遺された陰陽五行の理によるものであつて、澤田健氏がその門人に古典の遺産「五行の色体表」を壁間に掲げしめ、之を眺めしむることにより首練自得をせまられた所以があるのである。達人の域は「曰く言ひ難し」であり、「名状すべからず」である、ただ高度の五官の練磨によつて体験会得するより他に途はないのである、悟るよりほかないのである、五行の色体は次の通りである。
| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 性を示す |
| 五腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 | |
| 五官 | 眼 | 舌 | 唇(口) | 鼻 | 耳(二陰) | 前陰(生殖器と尿道) 後陰(肛門) |
| 五充(主) | 筋 | 血脉 | 肌肉 | 皮毛 | 骨 | 五臓の栄養を補充するもの |
| 五華 | 爪 | 面色 | 唇(乳) | 毛 | 髪 | 五臓精気がつく色沢に発するところのもの |
| 五季 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 | 季節の自然的配合 |
| 五方 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 | 方位の必然的配当 |
| 五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 | 色の理論的配列 |
| 五香 | 臊 | 焦 | 香 | 腥 | 腐 | 体臭の自然発生的なもの |
| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹 | 食味五臓の要求するもの |
| 五気 | 温 | 熱 | 湿 | 燥 | 寒 | 各臓の傷害する外気性状 |
| 五志 | 怒 | 笑 | 思 | 憂慮 | 恐 | 五臓の発する感情 |
| 五精 | 魂 | 神 | 意智 | 魄 | 精志 | 精神の配属 |
| 五役 | 色 | 臭 | 味 | 声 | 液 | 各臓の受持ちの色の役割 |
| 五声 | 呼 | 音 | 歌 | 哭 | 呻 | 病人の出す声 |
| 五音 | 角 | 徴 | 宮 | 商 | 羽 | 音階 |
| 五調子 | 双調 | 黄鐘 | 壱越 | 平調 | 盤渉 | 調子 |
| 五位 | 震 | 離 | 坤 | 兌 | 坎 | 八卦の方位 |
| 五星 | 歳星 | 熒惑星 | 鎮星 | 太白星 | 辰星 | 五大惑星 |
| 生数 | 三 | 二 | 五 | 四 | 一 | 五行生成を示した |
| 成数 | 八 | 七 | 十 | 九 | 六 | 数理の原則 |
| 五穀 | 麦 | 黍 | 粟稗 | 稲 | 豆 | 五臓の薬用としての穀物 |
| 五畜 | 鶏(犬) | 羊 | 牛 | 馬 | 豕 | 五臓の薬用としての家畜 |
| 五菜 | 韮 | 薤 | 葵 | 葱 | 藿 | 五臓の薬用としての野菜 |
| 五果 | 李 | 杏 | 棗 | 桃 | 栗 | 五臓の薬用としての果実 |
| 五兄弟 | 甲乙 | 丙丁 | 戊己 | 庚辛 | 壬癸 | 十干の配当 |
| 五募 | 兪 | 経 | 合 | 井 | 滎 | |
| 五親 | 水子 | 木子 | 火子 | 土子 | 金子 | 五行の相生 |
| 五液 | 泣 | 汗 | 涎 | 涕 | 唾 | 五臓所主 |
澤田健氏の望診は実は「五行色体表」に依據すると思はれる節が多い、「黴毒はカビだ、病人がカビ臭かつたら黴毒だ」と澤田氏が云ふて哄笑をかつたことがあるが、澤田氏に云はせれぱ笑ふものを冷笑したくなつたかも知れぬ、白楽天ではないが、身後金を推むよりも若かず生前一杯の酒で、酒の味の分らぬ奴に酒の講釈をしてみたつて分るわけはない。鹿児島名産の「カルカン」のいふ名菓があるが、あの風味といゝ、舌ざわりといゝ、味わいといゝ、頬の感触は喰つたことのないものにいくら説明しても分る筈のものではない。もうーつ食ひ物の話ばかりで恐縮だが、石狩川からとれた、生きてゐる鮭の脊にあるメフンの生まのまゝを生醤油で喰ふ味のよさも経験のないものは分らぬが本当だ、世の中はへんてこなもので、分らぬやつが、分る者を笑ふことがまことに多いのは困つたものだし、本当のも、科学的なものゝ創見が日本には少い理由もこゝにあらう。
話がよこにそれたが、「五行色体表」にしてもその通り、実地にぶつかつたものでなければ分りつこない、その訳はともかくも、先哲の遺したものを一応はそのまゝ受入れて患者について実験するといふ科学的態度をもつてのぞまず、低級な常識で抽象的に判断して、そんな馬鹿げたことがあるもんかと研究もせず、実験もせず馬鹿にしてかゝるのは馬鹿にしてかゝるものが馬鹿なので、馬鹿につける薬がないのと同様ほつたらかすより仕方がない、そんな人聞を澤田健氏は「人間のカス」とよんでゐる。我々は「五行色体表」を治療の前提とし、治療に役立たせて使へばよいので。「五行色体」の如何なるかについての文献的、歴史的研究は後でゆつくりやればよいのだ、もつとも我々はこれに関する定見をもつてゐるが紙数もないので今は省略する。要は治療の為めのものとして受取り、これを臨床に使へぱよいのだ。
さて、五行の色体の見やうだが、各目を横(※この画面では縦)に見て合致してゐれば順であるが、変つてゐれば逆である、順は悪候のやうに見えても治し易いが、逆は治しにくいのである。
例へば体臭が臊(あぶらくさい)で眼をつぶつて眼険がビクビク(筋)すれば肝胆の病気ではないかと証をきいて見る、体臭が腐(くされくさい)く、皮膚の色が黒く、何んとなく、へりくだり、びくびくする(恐)やうな、そわそわするやうな様子であれぱ腎の病気ではなからうかと当りをつけるのである。そして他の証と参互してみる、これがピタリと当るのである。
かやうにして、病人を師匠として経験をつめぱ、自然と悟り、会得するに至るものなのだ。東洋医術の立ち人を念願するものはこうした修練によつて達せられるのだ、これは望診ばかりでない。他の診法に於いても同様云えることがらである。次に古典にある望診の知見を少しく示そう。
- 青きこと草滋の如くなるは死す、翠羽の如きは生く。
- 黄なること枳実の如くなるは死す、蟹腹なるは生く。
- 黒きこと炲の如きは死す、鳥羽の如きは生く。
- 赤きこと衃血の如きは死す、雞冠の如きは生く。
- 白きこと枯骨の如きは死す、豕膏の如きは生く。
- 青黒は痛みと為す。
- 黄赤は熱と為す。
- 白きは寒と為す。
- 赤色両顴に出で大さ拇指の如き者は病小なりと雖も必ず卒かに死す。
- 黒色庭に出で大さ栂指の如くなる者は病まずして卒す。
- 赤多きものは熱多し。
- 青多きは痛み多し。
- 黒多きものは久痺を為す。
- 黒、赤、青皆多くあらはるゝものは寒熱を為す。
- 身痛み面色微黄、歯垢黄にして爪甲の上、黄なるは黄疸なり。
- 産婦を験するに、面赤く舌青きは母活き子死す。
- 産婦の面青く舌青く沫を出すものは母死して子活く。
- 唇口倶に青きは母子倶に死す。
- 爪甲紫色なるは血液凝渋し、手足厥冷す。
- 足扶裏腫れ、眼瞳子転ぜず、身悪臭あるは死す。
さて、色候、人種によつて異るであらうとの疑問があらう、もつともなことである。黄色人、黒色人はそれぞれ黄色黒色ながら五色を有してゐる。横山大観画伯の富士山の墨絵は黒ながら白もあれぱ赤も青も黄もある、墨絵だから黒いとは限らぬ、色候にしてもその通りである。
(二)聞診
五昔を聞いて其病を別けるのが聞診の原義である。その他、咳嗽、喘鳴、吃逆、五声(呼、音、歌、哭、呻)五音、角(3.4.牙音)微(5.歯音)宮(1.7.唇音)商(2.舌音)羽(6.喉音)腹鳴等を聞いて病を察するのが聞診である。(上例は呂旋法長音階を示す)
五蔵に声あり、声に音(舌のあてかたによつて異る音の出ること)ありといわれてゐるが。
- 肝声は呼、音は角に応ず調て直にし音声相応ずれば病無く、角乱るゝときは病肝に在り。
- 心声は笑、音は微に応ず、和して長きは音声相応ず、病無し、微乱れぱ病心に在り。
- 脾声は歌、音は宮に応ず、大にして和なれば音声相応じ無病なり、宮乱れば病脾に在り。
- 肺声は哭、音は商に応ず、軽くして勁けれぱ音声相応じて無病なり、商乱れぱ病肺に在り。
- 腎声は呻、音は羽に応ず、沈にして深けれぱ昔声相応じ無病なり、羽乱れぱ病腎に在り。
猶ほ、五蔵の五声、五音の清濁に応ずるを以つて、或は互に相勝負し、或は其音、嘶嗄する類を聞いて其の病を別つべきであるといふてゐる。 - 哭し、すゝばなたれ、鼻ひるものは肺の病。
- 笑つて、よだれ多きものは脾の病。
- 怒りつぽく、よぱわり、涙多く出るものは肝の病。
- 唾多く吐き、呻くものは腎の病、腎虚なり。
- 汗出で、たわごとつくは心の病なり。
- 声の軽きは気弱なり。
- 声の重濁なるは風気の痛なり。
- 声たたぬは肺に病あり。
- 声急なるは神の衰。
- 声塞るは痰。
- 声ふるふは冷。
- 声むせぶるは気の不順なり。
- あえぐは気の促なり。
- あくび多きは気の滞りなり。
- 声高く、口はやきは邪気の実。
- 声低く云ふこと遅きは正気の虚。
- 物を云ひさして息をつくは少気。
- 言ふこと息短く、下より衝き上ろやうなるは短気。
(三)問診
問ふて之を知るといふのは、其の五味の欲するところを問ふて、其の病の起るところ、在るところを知ると難経には云ふてゐる。
- 酸は筋に走る、多く之を食すれば人をして癃たらしむ。(肝也)
- 鹹は血に走る、多く之を食すれぱ人をして渇せしむ。(腎也)
- 辛は気に走る、多く之を食すれば人をして洞心たらしむ。(肺也)
- 苦は骨に走る、多く之を食すれぱ人をして変嘔を発せしむ。(心也)
- 甘は肉に走る、多く之を食すれぱ人をして悶心たらしむ。(脾也)
つまり、五味の中、偏嗜又は偏して多食するの物を問ふて、臓気の偏勝偏絶の候あることを知るといふのである。
又親族看病の人の言ふ所と合ふや否やを問ふべし、病人が病を重く自らいふは多くは実である。病人が病を軽く自らいふは多くは虚である。
この他、病苦、自覚症、既往症、経過、屎尿、等を聞きただすところの診法である。
(四)切診
難経では切脉して之を知る者は其寸ロを診し、其の虚実を視、以つて其の病を病ましむること何んの蔵府に在るかを知るなりといふてゐる。これは六部定位の脉診によりて陰陽臓腑虚実を知るの方法をいふのである。望診に秀ひでたる澤田健氏に比ぶべき九十翁八木下勝之助先生は実に近世に於ける脉診の名人であつた。翁は脉に従ひ一切患者の言をきくことをせず、「病人は世まよいごとをいふてゐるものだ、そんなことを聞くより、脉の方がちやんと病気を教へてくれる」と、何遍となく余にも云ふたものだつた。
こんな逸話がある。
或るとき肩凝りだから鍼をしてくれいふ浜の漁夫が来た、翁は脉を見て、鍼を執らず「お前さんには死脉が出てゐるから、お前さんには鍼をしませんよ」と云ふた。ところがその漁夫は大そう立腹して「とんでもないことを云ふ老爺だ、高が肩が張つた位で死んでたまるもんか、年をとるともうろくするもんだ、もうろくするにも程がある。こうピンピンしてゐる者を死ぬなんて」と隣り近所へふれ廻つたものだが、半年ぱかりしてぽつくりと死んだといふ。もう一例これは余の弟子の某君だが、試験も受け合格し、郷里に帰つて開業するについて余のすゝめで、八木下翁の治療所を見学しながら、身体があまり丈夫でないので治療を乞はしめた、ところが翁は脉を診て「これア、あんた、人の病気を癒すどころではないですよ、大変な躰だ、よつぽどみつちりあんたの躰に治療しなけれぱ、とり返しのつかぬことになりますよ」と云はれたといふ。ところで本人はそれほど感ぜす、鍼や灸をしながら治療するなら差支えなからうと、郷里に帰り開業した。幸か不幸か、所謂、経絡治療で、沢山患者も来、一人では手が廻りかね、教員をしてゐる妻君まで、東京に出して免許をとらせるほど繁盛した。が、一歳を出でずして不帰の客となつたのである。名人芸に達すればこのやうにおそろしいものである。我々は実にこのやうな生き証人の示した先人の遺訓を忠実に実践することによつて治療成績をあげてゐるぱかりでなく、この道は我々のみの独専すべき道ではないと信ずるが故にこれを公開し鍼灸人をして一人でも多く社会の病人を癒やしめ、社会に福祉を与え、鍼灸の価値を認識せしめ且つ高め、世界に示す科学的医術たらしめんとの微志のもとに筆に舌に叫んでゐる次第なのである。話は又ぞろそれたが、脉診の実際性はやつてみたものでなければ分らぬのである。
脈診のことは後述するが、切診は脈診のみではない。腹診、背視、四肢経絡診が含まれ、手指感覚によつて、動気、痞塊癥瘕、瘀血塊、硬結、圧痛、知覚過敏、陥下無力、溢隆、緊堅、血絡横居、脊椎凸出、陥凹、左旋右旋、左転右転等の異常を知ることにより、陰陽虚実を弁じ、臓腑経絡のいづれの病なるかを知らんとする診法なのである。
イ、脉診
脉診は漢方医学の最も特徴とするところで殊に東邦医学に於ける後世派医学の最も重用視するものである。
現代医学が心臓を最も重要視し、聴診器によつて、その機能を生態の事実のまゝに把握せんとする態度と通ずるものである。
脉搏は心臓の一縮一張によつて生ずることは古今の常識である。脉は従つて心臓の外候と云はれ、脉の状態は即ち心臓の状態を知るものである。洋法医学が心臓を大事にし、東邦医学が脉を大切にするはその軌を一にするものと思はれる。
脉象は心の作用に種々なる身体的環境がかさなり合ひ組合つて人間の生機を示すものである。
春夏秋冬によつて我々の生活体は異ふものである。冬は寒く、夏は暑い、冬は四肢末端の血管縮小するが故に脉は沈み細る、夏は拡張するが故に血管は太く洪となる、それが自然のまゝである、冬に夏脉即ち太く洪の脉をあらはす人はその人の内外の環境即ち全体の身のありやうは夏の状態に置かれてゐると同じ状態たることを物語るものである。反対なことが、夏に冬脉をあらはす人に云える。即ち、冬に夏脉洪を現はすは熱ありと見られ、夏に冬脉を現はすは寒なりと見られた、これも自然の理である。
一日のうちにも身体の状態によつて異る、入浴前後の気持が異るが如く、脉も異る、静坐と疾走後との脉の異るは誰れでも知つての通りだ。静座や驚恐悲哀等によつても心脉に影響することはこれ又人の知るところである。びつくりしたり、驚ろいたり、嬉しかつたりすると心臓の鼓動が高鳴るは誰れでも知つてゐる。 青春の若人が、おほげさに胸に手をあてる図は自然の動作としてよく見受けるところだ、犯罪捜査に又は嘘偽の有無を検するに実験心理学ではとつくに取上げてゐる点もこゝにある。自然なりや否やを環境と行動に於いて、その喰違ひを見出すことによつて鑑定するのである。
漢方の脉診もこのやうに経験的に実験して、集積し、分類し、意味づけしてこゝに我々の時代にのこされた。先哲の遺産である。軽々しくこれを非科学的なりとてすて去るべきものではない。よくよく吟味し古人の行ひし道を実践にうつさねばならない、自分の技倆が判別の能力あるや無きやも省りみず、又その能力に達せんとの努力もせずに、これを、迷信邪説とする態度ほど 非科学的な態度はない。
脉は一息に四動搏つが平人(健康人)とされてゐる、今日の医学と同じだ。我々はこうした自然認識に立つて先哲の道を履み道の高きに至らんとする者であり、且つその臨床的効果を信ずるが故に敢えて世に問ふ所以でもあるわけだ。

我々は前出三部九候の脉を前提とし病の陰陽虚実臓腑経絡を決定する所以のものも又如上の信念に立つに外ならない。
六部定位(じようい)の配当にば古来種々なる説がある。男女逆位を説くのも近世にあつたが、典據のないものである。我々は実際の臨床家の手振りを信ずるが故に掲出のものを取る所以である。要は「治療の為めの学問である」これが、我々の求道の據る精神である。臨床に用なき学問は今の我々にはどうでもよいのである。
さて、前掲の図を説明する。これは只今の橈骨動脉部を指触して見るのである。この部で五臓六腑の陰陽虚実を診るといふなら、さぞ奇怪に思ふ仁もあらう。が、古人はこれでやつて来た。それに基づいて治療の方針を立てゝ来た。「治す為めの前提」として我々もやつてゐる。臨床的に奏効を呈してゐる、だからこの通りやつてみられたいといふまでゝある。論議は証明を経てからのことである。実験してみてからのことである。定理はかくして確立する。
図中寸ロといふのは腕関節横紋の上位であり、こゝに一本の指腹をあてる、関上はその次に、つまり橈骨茎状突起の前側になるところに、寸ロにあてた指とならべてつける、尺中は同様関上につけた指にならべてつける訳である。
つまり、示指、中指、環指を三本揃へてその指腹を橈骨動脉部につけるやうにするのである。
図のやうに左右を六部位にするので、これを六部定位の脉ともいふ。そして、これを診る方法だが、一部に対して(一本の指で触つてみて)軽く(浮)、やゝ按へ気味に(中)、少しく強めに(按)おさへるのである。これを、浮、中、沈といふのである。一部に三つの押しやうで候ふから、三候である。これが片側で三部あるから三部九候といふのである。脉を伺ふこと五十動の間指を切してをくのである。
浮法で図中の腑を候ふ、沈法では臓を候ふのである。腑は陽で上にあり、表にある、臓は陰で下にあり裏にあるから、腑を見るには浮めて軽く診、臓を見るには重めにして沈めて診るのである。中法で穀気(胃気)の脉を候ふとされてゐる。
右手の寸ロには図に示すやうに、大腸、肺、関上には胃、脾、尺中には三焦、心包、命門、左手の寸ロには小腸、心、関上には胆、肝、尺中には膀胱、腎として、これを候ふのだが、浮法で 腑を、沈法で臓を候ふのである。例へぱ右手の寸ロを浮めて診れぱ大腸を、左手関上を沈めて診れば肝を候ふといふ訳である。こうして、指で触つてみて、力があるか(実)、力が無いか(虚)で 臓腑の虚実を決めるのである。臓腑の虚実さえ決まれぱ、後述の治穴配合が決定出来、後は補瀉の手法によつて鍼なり灸なりを施せばそれで治療が出来るのである。第一図は後出「五行要穴図」と合せて、すぐ要穴が出るやうになるのである。
診脉の心得として昔しから次のやうに云はれてゐる、医者の手指を端正にし、心気を沈め、脉にとらわれることなく、脉を考へず、虚心坦懐にその応ずるところを感得するのである。指を浮めて指に通ふは気の往来である押して力あり、大なるは気の実、力なきは気の虚で、衛を候ふのであり、腑を候ふのである、指を按めて力有るは血の実、力なきは血の虚これ営を候ふのであり、臓を候ふのである。気血営衛については出説した通りである。
又、病人の脉に触れると同時に脉部に於いて、皮膚、皮下組織、筋肉の潤枯(栄養状態)を診、これによつて体質、素質、全身の栄養状態、筋緊張状態を察知するのである、これを脉外を候ふといふ。
水府の侍医、原南陽先生が「健脉を三ヶ年診て病人の脉に及べ」といふてゐるが、いかに修練を要すべきかはこれにて知ることが出来やう。
脉は診るものゝ気持によつて、細と思えば細く見え、結と思えば結ぱれて見ゆるものだから、 心にこれを見ず、思はず、ただ応ずるを察せよといふてゐるが、味ふべき言で、思惟を以つてせず、直観的な把握の方法をせねばならぬ、運転が手に入れば意識せずに、自転車でも汽車でも自動車でも無意識に反射的に操縦が出来るやうに百練自得によりて会得せらるゝ境地を古人は望んでゐるのである。
胃気の脉は穀気(元気)を候ふの脉で、中ほどの強さで押へ候ふことによつて得られるものである。胃は土で、中央に位し、和緩なるをとうとぶ、胃気の脉幽ならぱ死近しと知り、絶えたならぱ急死と知るべしといふ。胃気虚せば水穀化せず、元気衰へたると知るべしと、胃気の脉は若人にて五日や十日の病にては無くならぬが、久病労瘵久痢、腎虚老人には衰退することの多いものである。又、胃気の脉は肺は肺ながら、胆は胆ながらの脉あるを胃気の脉ありといふ。肺脉胃気の出でざるは不順にして病なりとす。
寸ロは魚際より一寸の分に、尺中は尺沢と魚際との間を一尺として下の一寸の分を、関上は寸位から三分、尺位から三分の分をもつて関部とす、つまり尺部は七分、関部は六分、寸部は六分の分にあるといわる。
難経には脈の軽重に肺部(三菽の重さ)心部(六菽の重さ)脾部(九菽の重さ)肝部(十二菽の重さ)腎部(十五菽の重さ)に於いて按ずべしとある、この心をもつてせよとの事である。
古来脉をいふには二十四脉、死脉、怪脉等がある。更に陽脉七表之脉(浮、芤、滑、実、弦、緊、洪脉をいふ)陰脉八裏之脉(微、沈、緩、濇、遅、伏、濡、弱脉をいふ)九道之脈(長、促、短、虚、結、牢、動、細、代脉をいふ)に細別する。が、詳細は別著にゆづり、こゝには最も使へるもので要穴図を配合するに足る祖脉を述べる。
祖脈は「おや脉」ともいふて浮、沈、遅、数の四脉であり、これに、虚脉、実脉が分れぱ、先づ脉はとれる。次にこれをのべよう。
| 祖脉 | 脉象 | 証 |
|---|---|---|
| 浮脉 | 表、陽にある脉で、軽く指を切し、膚と肉の間を押へるやうにする、軽く押へて有餘、強く押へて不足する脉 | 陽、表、風、虚をあらはす力あるは実―邪気外感(風邪)力なきは虚―元陽之虚也 |
| 沈脉 | 裏、陰にある脉である軽く押へてふれず強く押へて有餘の脉である | 陰、裏、湿、実をあらはす力あるは実(積)陽気実力なきは虚(気)精血虚脱 |
| 遅脉 | 一息に脉来ること二又は三搏よりうたぬものをいふ、来ること遅き脉なり | 寒、陰、湿(邪)積滞をあらはす力あるは痛、積力なきは寒、痒 |
| 数脉 | 一息に脉来ること五搏以上のもの、来ることの速い脉である | 数は進なり、陽、熱、火、燥をあらはす力あるは熱力なきは瘡 |
| 虚実 | 脉象 | 証 |
|---|---|---|
| 実 | 浮沈倶にあり、触つて力強く感ずる脉なり、指下迫りて緩かならずしてみのる脉 | 実、凝滞、毒、火をあらはす浮沈倶に実あり虚火に生ずるものあり |
| 虚 | 浮沈倶にあり、触つて力弱く感ずる脉なり、指下軟なり | 血少、傷暑(脱気)心血虚なり |
以上の脉から病人の脉を診て結局は虚実を決めればよいのである。例へば、左関上の脉を見て、指下、浮法で診て浮脉を得、数脉で力あれぱ、胆の実であり、遅脉で力なければ胆の虚脉である。沈法にして力あれぱ肝の実であり、力なければ肝の虚である。
他の部位もかやうにして虚実を弁ずれぱ、補穴、瀉穴がこれによつて出されるのである。後は補瀉すれば治療は終りなのである。
それから、死脉は一応心得て置く必要がある。 死脉あらはるゝ時は鍼灸を施さぬのが本道である。七死脉と称せらるゝは次の如きものである。
- 死脉
- 弾石―石を弾くが如く、息数次第なし、
- 解索―散乱して次第なし、
- 雀啄―鳥の啄むが如く、数急に連り来るもの、
- 屋漏―雨漏りの二三滴して絶ゆるが如きもの、
- 蝦遊―脉来りて動かず、しばらくして去つて後又来るもの、
- 魚翔―遊魚の頭定まつて尾をのみ揺が如きもの、
- 釜沸―湯の沸き立つて沸泡のあるが如きもの、
以上七種の脉が出たら、死脉として鍼せず灸せざるものであつた。
ロ、腹診
腹診は内経に起源したが中国ではあまり発達せずして、日本に於いて古方漢方医家の強く提唱したものであつた。腹診法は腹診によつて得た所見を直ちに治療の指示にせんとしたところに特長がある。
殊に吉益東洞先駆となり門人瀬丘長圭は「診極図説」を著し、腹診上留意すべき部位、所見をのべた。又、稲葉文礼の「腹証奇覧」和久田意仲の「腹証奇覧翼」多紀元堅の「診病奇侅」等は有名な著書である。
鍼灸界に於いては上述せる如く専ら脈診による証決定によりて治を施せるもの多く、腹診によるものは少かつた。が、「夢分流」の「鍼道秘訣集」及び著者未群の「獲麟籍」位である。これ等は腹部に臓腑を配当してゐるところが、後世派的である。
腹診を為すに患人を仰臥させ、両足を伸ぱし、両手を外股につけ、先づ、虚里を候ふ五六息動を候ひつゝ患人の気をしづめ、次に上腹のところを押へ、静かに左右を候ふ、押へて病人心よがるは虚なり、押へて痛むは実なり、軽く押へて痛むは邪表に、重く按へて痛むは邪裏にあり、臍上臍下平均してさわりなく、胸下すき、臍下ふわりとふくれ押へごたえあるは腎精の実で無病の徴で、臍下すき、たて筋あるは精虚である、病なきやうなれど病人なり。開元の穴は天の一元の気を候ふ、一身の太極、腎間の気を候ふ、こゝを人の生命、十二経の根本、三焦の気を候ふところとする。次に心下、三脘、小腸、陽明、両脇、臍中を候ふ、殊に募穴は丹念に診るべきである。
次に主要なる腹診の目あてをのべよう
- 鳩尾――心臓を配す、邪あれば目眩、舌病、頭痛、不眠、睡中驚き、怔忡、心痛。
- 不容――脾の募とす、脾臓の病を知る、こゝに邪気あれぱ乎足、唇の病、両肩痛む。
- 期門、腹哀――肺先とす、脾募の両傍、茲に邪気あるときは息短、喘息、痰出、肩臂の病あり。
- 章門――及章門の上下を肝の蔵とす、こゝに邪気出れば眼目の痛、疝気、気淋、胸脇攣痛、短息、短気にて酸きものを好む、足の筋攣ること屡々あり、諸病寒気するは皆肝の業なり肝瘧は此処に邪気あり、針して邪を退るときは癒る。
- 鳩尾と臍との間――こゝを胃の腑とす、万物土より生じ、土に入る。胃腑飲食の入る為に実易く、実によつて邪気となる故に草臥れ眼を生じ、扨は胃火熾なるが故に食物を焼き胃乾くにより食を沢山に好み喰ふ、其の終りは手足腫れ土困しめぱ腎水を乾し脾土へ吸取られぬにより、腎水共に乾き火となり邪と変じ小便止る。
- 実之虚――臍上実し、臍下虚無にして力なき腹なり、上気、短気、食後眠来、気屈し易しく、ため息あくび、肩胸痛むことあり、脾胃実腎虚なり。
- 虚之実――臍上虚、臍下実なり、無病なる人は吉、病める人は腹下るか、腰痛む、小便不通、淋病、大便結、女は帯下あるが、経閉、疝気、瘀血、湿邪を受け寒込みたるなり。
- 実実――臍の上下共に邪気あるをいふ、心痛、大食傷、急病、頓死などの腹なり。
- 虚虚――臍上下皆虚なる腹なり、最も悪しく、虚労等に出る腹なり、病人を草臥させざるやう針すべし。(以上鍼道秘訣集)
- 虚里(心尖搏動部)――動ありて痰飲、傷寒、熱病あれば重症。
- 中脘及臍の左傍動悸高きものは胃の気絶重症。
- 臍の上下動気あるもの腎気逆上難症。
- 水分穴動気あれば外邪、動気低きは内傷。
- 臍の右天枢の辺動気あれば瘀血。
- 臍の左天枢の辺動気あれば表邪。
- 上下三脘の左傍動気細数し肋中に上るは蛔虫。
- 左右胃経大筋あるは脚気、足痛。
- 左日月、期門結穴に塊状あれば癇症、神経質、口苦、寒熱往来、胸脇痛。
- 右不容の辺から下筋張るは痰症、気塊。
- 右大横の辺の塊りは尿病、淋疾、茎痛下疳、水毒。
- 左幽門のこりは頭痛、項強、悪寒、発熱、体痛(以上経験方による)
- 臍上に大さ臂の如く上り心下に至るは心積(伏梁)久しく愈へざれば煩心を病む。
- 左脇の下、覆杯の如く大小本末あるは肝積(肥気)久しく愈へぎれぱ咳逆、痎瘧して己えず。
- 胃脘にあつて覆大盤の如きは脾積(痞気)四肢、不収、黄疽を発す。
- 右脇下に杯の如きものあるは肺積(息賁)酒淅、寒熱、喘欬、肺壅を発する。
- 少腹に発して上り心下に至り豚の状の如く或は上り或は下つて時無し、腎積(賁豚)久しく痊えざれぱ喘逆、骨痿、少気なり(以上「難経」による)
治療に際してはこのやうな腹診と脉診とを参互して証を決定するのである。
ハ、切経、背視
手足三陰三陽並に久病には正経、奇経を触診し、皮膚及び皮下の異常を検するを切経といふ。
- 実は線状の硬結物、塊状、泥状物(瘀血)小塊の聚合物、棒状、板状、骨様塊等按圧して痛むもの等の触感あるものいふ。
- 虚は陥下、陥凹、手触れて痒感、局部的軟弱感、くすぐつたい感あるものは虚である。
これ等の感覚は疾病時には殊に顕著にあらわれるもので、痔疾に際しての上孔最穴、便毒には中渚穴、ゲキ門穴、下肢疾患には裏環跳穴、殷門穴、丘墟穴、上肢疾患には肩髎穴、欠盆穴、膏肓穴、頭病には天柱穴、風池穴等に多く実証の反応を肺結核の末期に肺経の陥下即ち虚証の反応を現はすのはその一例である。
ヘツド氏帯最高知覚過敏点、小野寺氏圧点等も経穴と一致するものであり、その相応ずる疾病の場合は実、虚の反応を現はすものである。(但し、経穴とヘツド氏帯とか小野寺氏圧点かととは本質的に異るものがある)
特に、原穴、ゲキ穴、絡穴等の変化の有無を丹念に診るべきである
背視は脊柱並にその両傍の肉理を診するもので、脊柱端正なるか、椎骨均整なるか、凸出、陥凹、左転、右転、転移等注意し、偏せるものは左右の虚実が出来るものだから、その虚実を正し、虚は補し、実は瀉するのである。又その第一行(脊際)を診して内臓の熱を見、第二行を診して臓の変化を、第三行を診して腑の変化を診する。
第九節 病証
鍼灸医術の本質的なるものは「随証療法」、とさへ謂はれてゐる。この証は対症療法の症ではない。単なる症候群の総合を謂ふのではない、況んや、病名をいふのでは勿論ない。現代医学とても、病名を決定せる後、実際具体的なる投薬、手術、治療に際しては医師の経験と手練によつて載書以外、又は書を以つて伝ふべからざる現実の方法によつて、即ち、書籍を飛躍した、論理を超えた、いはば、直観的手法によつて処理してゐるのではあるまいかそれは、手当ての生命に連るものであり。生命の機に対応するからである。
証とはこのやうに生命に根ざすものであり、治療の眼とするに足るものをいふ。「生命に直結する、生活体の現はす全体綜合的反応としての症候群中の主役」が証である。漢方医大塚敬節先生は「証とは単なる病状の綜合でなく病の理念的表現である、病者の症候群を『証』と考へると『証』の把握が愈々困難となる。『証』は撰択的であり、理念的である。写実的病状の羅列ではない、病状の最も大切なものゝ把握である」といわれてゐる。このやうに、治の為めに、その眼とする根本を活かす為めに、部分を捨象する理論であり、法則である。
従つて古書には写実的羅列的な病状を記さずして、治療の眼目として把握されねばならぬ『証』を示してあるのである。従つて我々は『証』を決定することによつて治療方則が立つのである。 こゝに古法鍼灸の本質的なる真髄があるのである。
脉外、脉証を按じて、主証を決定することも出来、治方を立てることも出来るのはこのやうな概念を持つ『証』に立脚して行ふからである。
我々は証によつて、陰陽虚実寒熱内外を決定し、これを五臓六腑経絡経穴へ還元し治療出来るのであり、これによつて、主治穴の配合を必然的に理論的に決め、後は補瀉の手技を行えぱよいのである。証とはこのやうに主要なものである、詳細は本間祥白君の「鍼灸病証学」及余の「鍼灸経絡治療講座」に譲り、茲にはその一般を示すことゝする。
(一)五運主病、六気為病(素問玄機原病式による)
五運主病は証によつて、その本を知ることの出来るもので、諸風掉眩は皆肝木に属し、諸痛痒瘡瘍は皆心火に属し、諸湿腫は皆脾土に属し、諸気膹鬱の病、痿は皆肺金に属し、諸寒収引は寒の用、冬寒すれば則ち拘縮し、これは皆腎水に属すとされてゐる。五行の主るところとさる。
六気為病は諸暴強直支痛緛戻裏急筋縮は皆、風に属す、(足の厥陰風木は乃ち肝胆の気なるによる)諸病喘嘔吐酸暴注下迫転筋小便渾濁、腹脹大にして之を鼓けば鼓の如きもの、癰疽、瘍疹、瘤気、結核吐下霍乱、瞀鬱腫脹、鼻塞鼽衂血、溢血、泄淋悶、身熱悪寒戦慄、驚惑悲笑、譫妄、衂衊、血汚皆、熱に属す(手少陰君火の瞀乃ち真心小腸の気なるによるとす)
諸痙強直、積飲痞隔、中満、霍乱、吐下、体重胕腫肉泥の如く、之を按じて起きざるは皆湿に属す(足太陰湿土乃ち脾胃の気なるによる)
諸熱瞀ケイ暴かに瘖し冒昧し、躁擾狂越罵詈驚駭。胕腫疼痠、気逆衝上し慄れて神守を失ふが如く、嚏嘔、瘡瘍、喉痺、耳鳴及聾、嘔涌溢して食下らず、目昧くして明らかならず、暴りに注ぎて、目閏ケイ暴かに病み暴かに死す、皆火に属す(足少陽相火して熱、乃ち心包絡、三焦の気なるによる)
諸澁枯涸乾勁皴掲皆燥に属す(手の陽明燥金なり乃ち肺と大腸との気なるによる)
諸病上下出るところ、水液清冷澄徹、癥瘕癪疝痛堅痞、腹満急痛、下利清白、食し己つて飢へず、吐利腥穢、屈伸便ならず、厥逆禁固皆寒に属す(足太陽寒水は乃ち腎と膀胱の気なるによる)
(二)正経自病(難経四十九難)
憂愁思慮は心を傷り、形寒飲冷は肺を傷り、恚怒気逆上りて下らざるは肝傷り、飲食労倦は脾を傷る、久坐湿地、強力入れば腎を傷る、これをもつて、傷らるゝの臓を知るを得べし。
(三)五邪所傷
中風、風は木なり、肝を傷り、傷暑、暑は火なり心を傷る、飲食労倦、脾は四肢を主る脾を傷り、傷寒、寒は金気なり肺を傷り、中湿、湿は水なり、腎を傷る、霧雨蒸気の類即ち湿なり、腎を傷るとさる。
これ等の邪が、五臓のどこを傷るかにより虚邪(後より来るもの)実邪(前より来るもの)賊邪(勝たざるところより来るもの)微邪(勝つところより来るもの)正邪(自ら病むもの)といふのである。
今心病挙例により難経の示すところをのべやう。
| 心病 | 知中風 | 其色赤 | 其病、身熱脇下満痛、其脉浮大而強 |
|---|---|---|---|
| 知傷暑 | 悪臭 | 其病、身熱煩心痛、其脉浮大而散 | |
| 知飲食労倦 | 当喜苦味也 | 其病、身熱而体重嗜臥四肢不収、其脉浮大而緩 | |
| 知傷寒 | 当譫言妄語 | 其病、身熱洒洒悪寒甚則喘咳、其脉浮大而濇 | |
| 知中湿 | 当喜汗出付加止 | 其病、身熱而小腹痛足脛寒而逆、其脉沈濡而大 |

次に臓腑病及び経絡病の病証をのべやう。
鍼灸古典に於いては臓脇病と、十二経病を知ることにより、その証を把握し、同時に補穴、瀉穴を載記するのが普通である。
次にこれについて、古典の示すところをのべ 、実際治療に便することゝする。
(四)臓腑病(井滎兪経合主治穴)
一、胆病(脉、弦)
「証」潔なるを善くし、面青くして、よく怒る
心下満(井)に竅陰穴。身熱(滎)に侠谿穴。体重節痛(兪)に臨泣穴。喘欬寒熱(経)に陽輔穴。逆気而洩(合)に陽陵泉穴。総べての場合は原穴である丘墟穴を用ふ。
二、肝病(脉、弦)
「証」淋溲し難きもの、転筋、四肢満閉し、臍の右動気あり。
心下満に(井)大敦穴、身熱に(滎) 行間穴、体重く節痛に(兪)太衝穴、喘欬寒熱(経)に中封穴、逆気而洩(合)に曲泉穴、
三、小腸病(脉、浮洪)
「証」面赤く、ロ乾き、喜笑する、
心下満は(井)少沢穴、身熱(滎)に前谷穴、体重節痛に(兪)後谿穴、喘欬寒熱に(経)陽谷穴、逆気而洩に(合)小海穴、総べての場合は原穴である腕骨を用ふ。
四、心病(脉、浮洪)
「証」煩心、心痛み、掌中熱し、臍上に動気あり、
心下満に(井)少衝穴、身熱(滎)に少府穴、体重節痛に(兪)神門穴、喘欬寒熱(経)に霊道穴、逆気而洩(合)に少海穴を用ゆ。
五、胃病(脉、浮緩)
「証」面黄み、よく噫し、よく思ひ、よく味ふ。
心下満(井)は厲兌穴、身熱(滎)に内庭穴、体重節痛に(兪)陥谷穴、喘欬寒熱(経)に解谿穴、逆気而洩(合)に三里穴、総べての場合は原穴である衝陽を用ゆ。
六、脾病(脉、浮緩)
「証」腹腸満し、食消せず、躰重く節痛み、怠惰し臥すことを好む、四肢収まらず、臍に当りて動気あり、之を按ずれぱ牢して若しくは痛む、
心下満(井)陰白穴、身熱(滎)に大都穴、体重節痛に(兪)太白穴、喘欬寒熱に(経)商丘穴、逆気而洩に(合)陰陵泉穴。
七、大腸病(脉、浮)
「証」面白く、よく嚔し、悲愁して楽しまずよく哭く。
心下満(井)に商陽穴、身熱(滎)に二間穴、体重節痛(兪)に三間穴、喘欬寒熱(経)に陽溪穴、逆気而洩(合)に曲池穴、総べての場合は原穴である合谷を用ゆ。
八、肺病(脉、浮)
「証」喘嗽し、洒淅として寒熱し、臍の右に動気有り之を按ずれば牢くして若しくは痛む。
心下満(井)に少商穴、身熱(滎)に魚際穴、体重節痛(兪)に太淵穴、喘欬寒熱(経)に経渠穴、逆気而洩(合)に尺沢穴を用ゆ。
九、膀胱病(脉、沈遅)
「証」面黒くしてよく恐れ欠伸す、
心下満(井)に至陰穴、身熱(滎)に通谷穴、体重節痛(兪)に束骨穴、喘欬寒熱(経)に崑崙穴、逆気而洩(合)に委中穴、総べての場合は原穴である京骨を用ゆ。
十、腎病(脉、沈遅)
「証」逆気し、小腹急に痛み、泄して下腫の如し、足脛寒して逆す、
心下満(井)に勇泉穴、身熱(滎)に然谷穴、体重節痛(兪)に太溪穴、喘欬寒熱(経)に復溜穴、逆気而洩(合)に陰谷穴を用ゆ。
十一、心胞病
心下満(井)に中衝穴、身熱(滎)に労宮穴、体重節痛(兪)に太陵穴、喘欬寒熱(経)に間使穴、逆気而洩(合)に曲沢穴を用ゆ。
十ニ、三焦病
心下満(井)に関衝穴、身熱(滎)に液門穴、体重節痛(兪)に中渚穴、喘欬寒熱(経)に支溝穴、逆気而洩(合)に天井穴、総べての場合に原穴である陽池穴を用ゆるのである。
以上が、臓腑病の証及びその治穴である。
(五)十二経病(井滎兪経合補瀉穴)
一、肺経病 (多気少血)補穴は太淵、瀉穴は尺沢
| 是動病 | 肺脹満して喘咳す。欠盆の中痛む、甚しい時は両手に支へて瞀。 |
| 所生病 | 咳嗽、上気、喘喝、煩心、胸満、臑臂の内前側の痛み、掌中が熱する。気分有餘あれぱ肩背が痛み風邪により汗出て、中風、小便数にして欠伸す。虚すれぱ肩背痛み寒し、少気にして息するに足らず、小便の色変じ失尿することあり。 |
二、大腸経病 (気血倶多)補穴は曲池、瀉穴は二間。
| 是動病 | 歯痛、頬腫、津液を主として生ずる病(下痢、秘結) |
| 所生病 | 目黄、ロ乾、鼽血、喉痺、肩前臑痛大指次指用ひられず、有餘すれぱ脈の過ぎる所が熱腫する、虚する時は寒慄して温まらず(気の不足) |
三、胃経病 (気血倶多)補穴は解谿、瀉穴は厲兌。
| 是動病 | 灑々然と振寒す、手足を伸し、欠伸して顔黒し、病至れば人と火を悪む、木音を聞けば惕然として驚き心動乱す、独り戸を閉ぢ窓を塞甚ぎしけれぱ高所に上りて歌ひ、衣を棄てて走らんと欲する、腹脹り、是を骬厥と云ふ。 |
| 所生病 | 狂瘧、温淫汗出、鼽血、ロ渇、唇昣喉痺、頸腫、大腹水腫、膝臏腫痛胸乳、気街、伏兎下腿外側、足跗の上痛み、中趾はたらかざるに至る。気盛なれぱ身の前皆熱し、気の胃に有餘する時は穀を消し善く飢へる、小便の色黄なり。気不足する時は身前皆寒慄し、胃中寒する時は脹満す。 |
四、脾経病 (多気少血)補穴は大都、潟穴は商丘
| 是動病 | 舌本強り、食すれば嘔ず、胃脘痛、腹脹り、善く噫す、後(便)と(風)気とを得れば病快然として衰ふが如し。身体皆重し。 |
| 所生病 | 舌本痛み、体の動揺不能、食下らず煩心、心下の急痛、寒瘧、溏(水瀉)、瘕泄(裏急後重)、尿閉、黄疸、臥すこと能はす、強く立てぱ膝股内水腫す、四肢冷厥すれば 足の大指用ひられず。 |
五、心経病 (多血少気)補穴は少衝、瀉穴は神門
| 是動病 | 咽乾く、心痛、渇して食を欲す、之を臂厥と為す。 |
| 所生病 | 目黄み、脇痛、臑臂後内側厥痛みし掌中熱する。 |
六、小腸経病 (多血少気)補穴は後谿、瀉穴は小海
| 是動病 | 咽痛み頷腫れて回顧するべからざるもの。 |
| 所生病 | 耳聾、目黄み、頬腫れ、頸頷肩臑肘臂後外側痛む。 |
七、膀胱経病 (多血少気)補穴は至陰、瀉穴は束骨
| 是動病 | 頭を衝いて痛む、目脱するが如し、肩痛み、腰折るしが如し、髀曲む可からず、膕結ぶが如く、腨裂くが如し。 |
| 所生病 | 痔瘧狂癲の病、顖頭頂痛み、目黄み涙出ず、鼽衂、項背腰尻膕腨脚皆痛み小指用ひられず。 |
八、腎経病 (多血少気)補穴は復溜、瀉穴は湧泉
| 是動病 | 飢えて食を欲せず、面黒く炭色の如し、欬唾すれぱ血あり、喝々として喘す、坐して起きんと欲すれぱ目が䀮々とし見得ざるに至る、胸部に力なく飢えたやうになる。気不足すれぱ非常に人を恐れる(是骨厥と云ふ)。 |
| 所生病 | 口熱し、咽乾き、咽腫、上気、咽乾及び痛、煩心、心痛、黄疸、腸癖(痢病)背臀股内後側痛む。痿厥して臥せんことを好む。足下熱して痛。 |
九、心包経病 (多血少気)補穴は中衝、瀉穴は太陵。
| 是動病 | 手心熱し、臂肘攣痛し、腋腫れ、甚しければ胸脇支満して心中澹々として大動す、面赤く、目黄み、喜笑してやまず。 |
| 所生病 | 煩心、心痛、掌中熱す。 |
十、三焦経病 (多血少気)補穴は中渚、瀉穴は天井。
| 是動病 | 耳聾渾々(にごること)、焞々(音きこゆること)たること、咽腫、喉痺。 |
| 所生病 | 汗出て目の銳眥痛み、耳後、肩臑肘臂の外皆痛む、小指の次指用ひざるに至る。 |
十一、胆経病 (多気少血)補穴は侠谿、瀉穴は陽輔
| 是動病 | 口苦く、よく太息し、心脇痛転側すること能はず、甚しき時は面に微塵あり、体に膏沢なし、足外反熱す。 |
| 所生病 | 頭角、頷痛む、目の銳眥痛み、欠盆の中腫れ痛む、腋下腫れ、馬刀俠癭す、汗出て振寒瘧、胸中脇筋髀外より脛骨外踝の前及諸節皆痛む、小指の次指用ひざるに至る。 |
十ニ、肝経病 (多血少気)補穴は曲泉、瀉穴は行間。
| 是動病 | 腰痛して俛仰すること能はず、男子は癲疝、婦人は小腹腫れ甚し時は咽乾き面塵き、色を脱す |
| 所生病 | 胸満し、嘔逆し、洞洩す、狐疝、遺溺(夜小便通せず昼は静かにして出る)、癃閉(尿不利)である。 |
(六)是動病、所生病と井滎兪経合原穴解
難経二十二難に脉に是動あり、所生病あり一脉変じて二病とあるが、これが、是動病、所生病といはれるところのものである。
是動病――気也――邪在気、気為是動――主呴之――気在外、気留而不行者為気先病也
所生病――血也――邪在血為所生病―――主濡之――血在内、血壅而不濡者為血後病也
前節栄衛の項でのべたやうに、気は衛気で脉外を循り、血は栄気で脉中を循るといふ、七十七翁恩田重信氏が『人体中に神気充満す気片寄すれぱ病となる、一切の万物は電気の中和によつて有す、中和電気が分離せば即ち電気発生せば病気となる、この電気を漢方の気と見ることが出来る』と云はれたことがあるが、かゝる意味の気が脉外を行き、血が之に従ふて循行するとの是はあながち荒唐無稽ではない、気は煦め往来し、皮膚分肉を薫蒸栄護し、血は筋骨を濡潤し、関節を滑利して臓腑を栄養するものとされてゐる。
気は外に在り、血は内に在る、こうした考へ方から、気は先きに病み、血は後に病を生ずるとも考へられた、とにかく、これについて古来から論説があるが、今は気病が是動病で、血病が所生病であるとして置いてよからう。
井滎兪経合原穴は十二経の各経にある穴の性質であつて、この解については難経六十四難、六十八難等に分明する説論がある。次にこれを紹介する。
| 井――水之原――所出――谷井水源であり 滎――水之陂――所留――ごく極かに小水であり 兪――水之竇――所注――転輸、転注するところであり 経――水之流――所行――経過して流るゝ流れであり 合――水之帰――所入――相会し諸流を合するものである |
かやうに十二経の各経にあるから、その性質によつて、具体的なる使用に供することが出来るのである。そして右に述べた解は所調、感触としての対象を示すものと考へてよいので、井は井源なる故、特殊の病状を呈せざる限り触れ難く、これを知るは古人分寸規定指示によるより致方がない。滎(ケイと訓むを本訓とす)は井源なり出でたる水の意にして、我々は所謂キヨロキヨロなる表現をつかつてゐる。然しながら、極めて絶小なるものである、兪はやゝ大なるもので、 我々はこれをギヨロギヨロと表現する、経はこれより大きく、コリコリといふし、合は大部大きいので、ゴリゴリと表現するのが常である。つまり、キヨロキヨロ、ギヨロギヨロ、コリコリ、ゴリゴリなる経筋をたよりにして経脈経穴を定めんとするのである。
猶ほ井滎兪経合の主治証がある。
| 井――主心下満(肝木病) 滎――主身熱(心火病) 兪――主体節痛(脾土病) 経――主喘咳寒熱(肺金病) 合――主逆気而泄(腎水病) |
従つて、右の主誰のあるときは井滎兪経合穴を使ふのである。十二原穴は各病相通じて用ひてよい。
猶ほ陽経と陰経によりて、井滎兪経合主治証穴の五行配当が異ふのである。即ち、陰経は井(木)滎(火)兪(土)経(金)合(水)であるが、陽経は井(金)滎(水)兪(木)経(火)合(土)である。これによつて、陰経の井穴と陽経の井穴とは木と金であるから相尅関係があることゝなる、井穴ぱかりでなく、他四穴に於いても同じやうに相尅関係になるのである。難経では、それを剛柔夫婦の道と説いてゐる、陰陽同じからざる故なりと説明してゐるが、これ等生体の神秘はやがて進歩せる科学によつて解明されることであらう。
又、七十三難に諸井は肌肉浅薄気少、使ふに足らざるなり、井を刺すべきものは滎を刺して之を瀉すべしとあるが、井を瀉すときときには其の子である火穴滎を瀉せといふことである。又井を補ふべきときは其母である合穴を補ふてよいのである。これは六十九難の子母の補瀉法の運用である。内経に「若得若失」といふ説があるのが『得』は「求而獲也」で佖然たらしめることであり、補であり、『失』は「縦也遺也」で恍然たらしめる、瀉となることを表はしている。
又四季によつて経気の循行に厚薄がある、七十四難には四季による経気の浮沈によつて次の如く述べてゐる。
春刺井(邪在肝)夏刺滎(邪在心)季夏刺兪(邪在脾)秋刺経(邪在肺)冬刺合(邪在腎)と云ひ、それぞれ四季により刺すべしといふのである。
第十節 鍼灸治療方法の種々相
鍼灸治療の実際を眺めると実際種々な方法のあることに気がつくであらう。一つの疾病、病証に対して種々雑多なやりかたがある、古書に於いても、その指示が、病類に示してある通りであるが、これ又種々なる方法がある、こゝで我々はこれ等の治療法が何を指示してゐるか、探求して見ねばならぬ訳である。
よく何病に対して何んの穴を用ふるとは、古書の示してゐるところであるが、初学の人は古典の通りに行ふて万全を期し得ると考へてゐるとせば危険である。これは医家の「治療医典」の取扱ひの如きものであつて、「治療医典」を取扱ひ、そこより摘出する治療法を掴み出すには、掴み出す側の撰択知識が必要なのである、これは基礎的知識であり、臨床的経験である、ズブの素人が医者の使ふ「治療医典」を大事ごせうに大切がつたところで撰択眼を持たねば猫に小判である、撰択眼が即ち基礎知識である。
古典に載せられてある病証の治方は採者たる鍼灸術者に一応基礎知識あるものとして述べられてゐることを忘れてはならぬ 、規範のない人には、そのまゝ古典通り行ふことは、全く鵜の真似をする鳥の類である。
ところが、実際はこのやうな鵜の真似をする鳥がそんじよそこらにうようよいてゐるからこそ、鍼灸術の真価が失はれ、その真の治療力が出渋るのである。
馬鹿のーつ覚えといふ俗言があるが、一つの方法、事柄で万事に通じようとするから間違ひが起るのである。ところが、御本人はそうは考へない。これで治らぬのは自分のせいではなく、鍼灸の治療を受ける病人のせいと軽く考へてゐるところに間違ひのもとがある。
人間は有機的なものであり、皆出来が異る、体質、素質、生活、環境、気候、風土、病気、病状、新久等によつて皆異るのである。異る相手をかわらぬものと考へるから、そもそも間違ふのである。
ところが世間は広いもので、このやうな一方法でのみの施術しかせぬのに門前市を為すの盛況を見せてゐる業者は決して少くないこれは我国の随処に見られる現象である。即ち「治らぬものは自分の治療に合はぬものか、どこに行つても治らぬ病」だとばかり、すまし込んでゐられゝば無事安泰である、この一流儀の治療法に適合する病人病証のみが治るといふ訳けである。これでは鍼灸される病人こそいゝ面の皮である。金は取られる病気は癒らぬでは立つ瀬があるまい。
真の鍼灸家は如何にしてこの病人を治すべきかに心胆をくだかねばならぬ、一方法のみで病気が治るものならば世に苦労はいらぬ筈である。我々は何んでもよい、 病気を治せぱよいのである。病気を治す方法をこの故に種々に知つてゐねばならぬと主張するは当然ではないか。
然もその方法が必然的に用いられるに至つた理論をはつきりと自覚する基礎知見を持つてゐねぱならない筈である、こゝに我々の古典的医術の提唱があるのである。
万人に対し万法を用ふによつて適正なる手技を施し、治療せしめんとするのが、即ち「経絡治療」の要諦なのである、けれども世に流行する所謂名家がある。こゝに、その概要を紹介することゝする。猶ほこれ等を点検するに、いづれはこの源を古人先哲の或る証に使用したものであることを歴史的に之を研究すれぱ明白となることであつて、現代の世に、独創独自の工夫創見と考へてゐるものがあつてもこれは歴史的系列のどれかに属することは、温故知新の今更ながら貴きことを泌々と感得するであらう、我々はこれを事実について検討してみたいと思ふ。
(一)鍼刺法の種々相
霊枢官鍼扁に「針大にして病小なれぱ気瀉すること甚だしくして却つて害を為す、病大にして針小なれぱ、針カ病に至らずして病気務瀉せざるなり、病骨髓にあるものは長針を以つて刺し、皮膚にあるものは短針を以つて之を刺すべし」又「病に浮沈あり病浅くして針深けれぱ良肉を破り病深くして針浅ければ病気瀉せず其理を過てば邪是に従つて益す、五臓を動かして後大病となる」とある。こゝに九鍼の法を立てたといふ、もつともなことである。が現代の鍼を行ふものを見るに、いかなる病にも大鍼や長鍼を振り廻して、得意然たる鍼医がゐる。然も相当流行させてゐるのがある。そうかといふて、短鍼のみより扱ひ得ず、又は大鍼長鍼を知らぬ鍼医さえあるのはどつちも困りものである、技術としてはいづれも精微を有するもであるから方とも習ひ覚えて置かねぱならないものである。(稽古法は後述する)然し、とかく世間は太い鍼や、長い鍼を刺すものの方が短い鍼を刺すものより技術長ぜりと考へ勝なところに一方は繁栄し、他方はあまりはやらぬといふ微苦笑ものが行はれてゐるのが実情なのだ。
素問、離合真邪論に「男は陽で気が浅く針も亦浅く天分に刺し、女は陰で気が沈むから鍼も深く地の分に刺すべし、又男女朝晩によつて気の所在異るにより気の所在を考へて鍼を刺さねぱならぬ」とか。
霊枢、根結扁に「貴人は肌肉軟かにして身体弱し、故に鍼を軽く、やわらかに刺し、賎者は筋骨強く皮膚厚き故に鍼深くして留むべし」とある。
霊枢、逆順肥痩扁に「六十七十以後は気弱く下虚し、精血へるが故に浅く刺して疾く針を発し、小児は本より肉脆にして血少く気弱し、是に刺すには毛を抜くやうにし、日に再び刺せど、深く刺すべからず」と又「肥たる人は血気充満し、肌膚堅固なり、若邪の加ることあらば此を刺すに深くして久しく留む、痩せたる人は皮肉薄く血気清滑にして気血脱し易し、故に浅くして疾く鍼を退くべし」といふてゐる。
霊枢、根結扁に「気の滑なる者は行い易きが故に浅く刺して疾く鍼を出すべし、気濇なる者は気の行ること遅きが故にゆるく刺して久しく留むべし」とし。
霊枢、官鍼扁に「針を三本も五本も刺して置き、一方より一本宛ぬくことあり、多くは寒邪の甚だしく沈んであるに用ふることあり好んでこれを用ふるべからず」とあるが、このやうな流儀即ち留置鍼(置鍼)をいかなる病人にも施して他意なき鍼医も全国には相当多いのである。
鍼灸要法指南にいふ「諸病いろいろありと雖も、其経の病む所を考へて井滎兪経合の要穴に唯一鍼にて補瀉迎随するあり、若くは二針三針刺すのみにて、満身に針すことを喜まざるあり、これ一流なり」と記してゐるが、これこそ、鍼医の上品といふべきであると、同時に満身に鍼していたづらに病人に痛苦を与へ気血を逆せしめる鍼医もゐる。
霊枢、終始扁に「急病は邪気入ること浅きが故に数々刺して浅く内れ早く効を求むべし、久病は病根篤きが故に深く刺して久しく留むべし、速効を求れぱ却つて禍を得るなり」とある、只一律一遍の鍼の運用のみを心得てゐるものゝ頂門の一鍼であらう。又同扁に云ふ「房事を行つて即ち刺すことなかれ、針刺して房事することなかれ、酔ふて刺すことなかれ、刺して酔ふことなかれ、怒つて刺すことなかれ、刺して怒るととなかれ、疲れて刺すことなかれ、刺して疲るゝことなかれ、飽食して刺すことなかれ、刺して飽食することなかれ、饑へて刺すことなかれ、渇して刺すことなかれ、大いに驚て刺すことなかれ、大いに恐れて刺すことなかれ、車馬に乗つて来るものは暫く休んで之を刺し、歩行して来るものは食する程の間息んで之を刺すべし」とある。今の鍼医かゝることを考慮に入れずに刺すは、自分の鍼のキキメを滅殺することに気付かぬが為であらう。
鍼灸要法に云ふ「假令は腹を痛み手もさわる事叶はざる時は三里、照海等にて是を引きやうやく柔らぎたる時腹に刺すべし、兵法に曰く鋭気を避けて其の脱気を討つ」と鍼法の秘語、考ふべき言である。
神応経、補訣直説扁に「共の実邪を瀉したるぱかりにて虚を補はざれば又本え復するものである。七瀉三補、三瀉七補、その病によつて異る」といふてゐる。一概の鍼刺は鍼立てでこそあれ、鍼医とは云はれない。
素問、邪真論に「邪は風寒暑湿等の外邪也、絡より経に入つて血脉の中に舎る、正は真気也、正気 邪気は水波の如し、血気本静かにして邪是を犯す、水本静にして風これを犯す、故に浪波の起るが如くにして邪気の至ること、よく行きて数々変ず、時に至り、時に去つて常の所なし、邪の微なる時に治せざれば、後盛にして治し難し、虚は気体虚弱なる者なり、たとえ其脉大なれど必ず虚なり。実は腠理密にして筋骨壮に元気つよく生れつきたるなり(これは実邪ではない)」
又、内経の処々に「実を実(補)する勿れ、虚を虚(瀉)すること勿れ」とある。これ等によつて鍼の操作と刺戟との関係に示唆深きものを与へてゐる。
鍼灸要法にいふ「病に標・本あり、先づ得るを本とし、後に得るを標とす、病は本を治すれぱ標をのづから愈ゆ。内経にも病を治す事に其本を求むとある。然れ共、もし急証あるの時はたとへ本病ありとも、其の急なる所の標を治し、而して其の本を治すべし、是を權道といふ、大抵は先づ本を治するを医治の肝要とす」といふ、証によつて標本を決し病勢によつて『標治法』『本治法』 の先後、兼治を考へるのが鍼医の本領でなければならぬ、そればかりではない、素間、上古天真論にいふやうに「名医は神気を冥々に察して疾の未だ生ぜざる所を見て治す、故に用小くして功多し、庸医は病と成るを見て治す、下工は其の己に衰るを見て治せんとす、渇して井をほるに似たり」とある通り、この境地までの道を実は見事に古人はつけてゐてくれてあるのである。
世の流行家は大鍼、長鍼、留鍼(置鍼)折鍼などで人気を呼んでゐる。が、これは一律一辺に施すべきものでないことは上述の通りである。お灸にしてもこういふことが云はれる、打膿灸、焦灼灸、さては、生薑灸、蒜灸、味噌灸、墨灸、漆灸、紅灸、油灸、婦人鍼灸家の人参灸となかなか、にぎやかなのがある。これとても、どの病人に対しても同一方法で行つてよいといふ ものではない、その特微とするところは勿論あるが、病は万態である。病に通合した方法で行ふべきが正当なる鍼灸の運用である。が、とかく世人は新奇を好む、目新しいもの、変つてゐるもの、奇なるものゝ流行するわけがこゝにある。鍼灸を商売と考へる人はこの点にも思慮をめぐらすがよい、が医は仁術であることを忘れずに、簡単に灸のことにつき次に紹介しやう。
(二)施灸法の種々相
イ、打膿灸
拇指頭大から小指頭大位の艾炷(あらかじめ紙筒につめて硬くなつたものを四、五分の高さに切つて皮膚に貼ずる)を燃焼させるのだが、まさに燃焼せんとするとき、両手の小指側で皮膚を圧へるのが法である、次に相撲膏を貼り、膿を出すのである、胸部疾患に第三胸椎の両傍、肩癖に膏肓穴、頭部疾患に肩外穴、臑会穴、腹部疾患に腎兪穴、胎毒、血液溷濁に三陰交穴、中気に外膝眼穴、横痃に青地博士家伝の臀部中央(グロツ氏三角点の辺)に穴を求むるの類である。
ロ、焦灼灸
これは疣、癰、疔、皮下蜂窩織炎、狂犬、鼠、蛇、毒虫の咬傷部、皮膚癩等の局部を徹底的に焼灼するに用ふるのである。原南陽の「砦草」に「病犬に喰はれゝば多く灸して狗牙の毒を焼尽し、其後解毒丸を用ゆべし」とある「内科秘録」には「本邦にては古く癰疽に灸炳す」とあるはこの焦灼灸のことである。
ハ、生薑灸、蒜灸、韮灸、杏仁灸
これ等は生薑、蒜、韮、杏仁等の切片又はこれを摺り潰して、泥状としたものを穴処に貼して、その上から、艾(良質でなくともよい)を燃焼さすのである。人参灸にしてもその通りである。殊に隔蒜灸、杏仁灸とて、癰疽、創傷面、咬傷に多く昔から使用されたものである。
ニ、味噌灸
これは御夢想灸とか、お姫様灸とかと云はれてゐるもので、厚さ二分位にお味噌の平たいダンゴをつくり、それを穴処に貼じて、その上からお灸を据えるのである。
ホ、塩灸
これは粗製の食塩の方がよく、穴処に食塩を置き(臍のやうなところはバラでつめるが、普通の皮膚面上には日本紙で包み、これを水でしめらして、碁石位にして)その上から灸するのである。人神気を失ひたるに昔しから臍中の塩灸が賞用されたものである。
ヘ、漆灸
生漆十滴、樟脳油十滴、ヒマシ油適宜をよくまぜて、艾に浸ませ肉池のやうにして置き、それを小さい箸先きで穴処につけるだけである。薬剤の調合にもう一つの方法がある。乾漆一匁、明礬十匁、樟脳五匁、艾適宜を粉末にして、黄柏の煎汁にて艾に混和浸潤させ前記のやうに穴処に点ずるのである。駒井博士の穴村の灸は漆灸であつて、患者は小児病が多いのである。
ト、墨灸
これも変つたやりかたである。先づ黄柏百匁と水一合との混和せるものを緩火で煎じて五勺とし、これで和墨を摺り濃汁とする、これを黄柏汁和墨といふ。次に、
第一法―黄柏汁和墨五勺位、麝香一匁、龍脳二匁、米の粉末二匁をよく混和して之を細棒で灸処に塗るのである。
第二法―麝香一匁、龍脳一匁、煤煙適宣をよく混和して艾に浸ませ、之を小豆大に丸めて(或は昔しの二銭銅貨位にして)灸処に置き、その上から灸するのである。この方法 は東北、北海道方面でよく使はれてゐる。
チ、紅灸
これは、わけのないことで、薬用紅を水に溶かして、それを穴処につけるのであつて、小児の疳虫等に百会穴、身柱穴等に行ふ、九州地方で行はれてゐる。
リ、油灸
これは、地方の老婆などのよくやつてゐるものであるが、目ぼし、肩コリ、踏み抜き等に用いる、昔の一文銭の真中に四角い穴がありてゐるが、その穴から、種油をしました燈心に火をつけて焼くのである。
その外に水灸、硫黄灸なるものがあるが、それは後日に譲ることにする。
(三)病気に対する治療穴の種々相
病気に対する治療穴にしても種々雑多である。⑴五指伸びざるには中渚穴、⑵眼の努肉かゝるには睛明穴、⑶耳聾気閉には聴会穴、⑷鼻衂には禾髎穴、⑸鼻塞不閉には迎香穴、⑹喘痰は天突穴、⑺婦人病一切には臍下三穴腰間七穴施灸刺鍼が「霊光賦」「方興輗」に記載されてゐる、このやうなことを挙例すれぽ際限がない。又拙著「一本鍼伝書」にも一本必治の標治的刺法を示しておいた。即ち、⑻鼻塞、鼻香を知らざるに印堂穴に下斜鍼に入れ鼻中に響けば鼻に通り、気持もよくなる、⑼耳鳴の時、頬車穴に前方に向けて刺し耳中に響けば、耳鳴りは少くなるか、止むものである。⑽五十肩とか、五十腕とか、寿命痛とかいわれる、俗に年うでといふもので、帯をしめたり、帽子をかぶつたり出来ないのに刺鍼して軽くすることが出来るが、手肘を屈伸して後側が痛めば、肩髃穴から、前側が痛めば肩髎穴から、いづれも、肩峰突起の下面に沿ふて刺入し、後から刺して前に響き、、前から刺して後面に響けば大抵、今までうごかなかつた、うでが楽くに多少はうごくやうになるものである。⑾肩胛間部がハル、コル、引きつるといふのに欠盆穴より後方を刺的するやうに鍼尖をむけて刺し、響が肩胛間部に達すれば(中間の響がないことが普通である)肩胛間部の異常は軽減するのである。⑿坐骨神経痛等のとき腸骨櫛後縁の上際に内下斜鍼三寸乃至四寸位刺入するか、臀部の外境の近くに指圧すれば大腿後側に響くところがある。この点に内上斜に鍼を向けて刺入すること一寸乃至二寸で大腿に響けぱ、おじぎの出来ない人でも楽くにお叩頭が出来るやうになる。このやうに「病気の近所に刺灸する」ことにより効果を期待するものがある、これは前記の標治法である。漢方古法は多分にこのやうな、標治的方法をとつてゐる。後藤艮山、香川修庵の灸法などはその代表的なものである。「後藤艮山五極灸」に臁瘡痔痒陰虫破瓜疥癬癜風小児白禿の如きは瘀血皮膚にあり、宜しく表の熱を開くべしとて、 これを開表といひ、脾胃和せず泄瀉して止まず、痰喘吐衂腸風下血するが如きは則ち臓腑に病あり、宜しく温動して之を動すべしと云ひ、労熱盗汗痃癖痞塊鬲噎反胃狂乱癲癇の如きは病の因るところ深し、根固蒂灸灼尤も多くして根底に徹せしむべしとて、日日月に数十乃至数万の灸を据々えべしといふてゐる。これを徹底といふ。
このやうに、刺戟療法と直ちに連る鍼灸運用の方法があつた。
ところが「病的なるものから遠のいた処」に刺灸して治効を奏してゐるものもある。⑴偏正頭痛に列欠穴、⑵気上りふさぐに足の三里穴、⑶心下の寒するに少沢穴、⑷股関節の疼痛に丘墟穴、⑸神性痴呆に紳門穴、⑹牙歯痛に呂細穴(腎経の太谿穴)⑺肚腹の病に足の三里穴、⑻腰背の病に委中穴、⑼頭項の病に委中穴、⑽面ロの病に合谷穴、⑾子宮出血に孔最穴、⑿腰間の病に崑崙穴、⒀側頭、身体の外側の痛み、引きつり、異和感に丘墟穴、⒁上実下虚で、のぼせやすく、目熱ぼつたきものに立たせたまゝで、崑崙穴、京骨穴に刺鍼施灸する類はこれである。更に、脉を按じ、陰陽五行の理に基づき肋間神経痛の如きに対し、木の陽実症の場合、手の商陽穴を補して肋間紳経痛が鎮痛し、肺虚で咳嗽、喘嗽に際して大敦穴を瀉することによつて、軽快するのは所謂本治法なのである。
このやうに、種々なる鍼灸治療法の相がある、いづれにしても、古典鍼灸の流れに掉さすものであることには相違ない。然も、標治法的直接的治療の方法は多分に刺戟療法的なものであり、刺戟のドーゼに重点を置き今の人のよく云ふ科学的なものである。が、本治法的なものは随証療法的なものであり、刺戟療法的理念を離れ、経絡に基づく治療法であると見ることが出来るのである。こゝに刺戟療法的な運用について蓮ぺたが、それでは、昔は刺戟療法的な考へを持つてゐなかつたかといふと、そうではない、次にその比較について述べやう。
(四)刺戟療法
大谷彬亮博士の「刺戟療法」に次のやうなことが記載されてゐる。刺戟の結果として現はるゝ身体的変化即ち生体反応は陽性相(Positive Phase)と陰性相(Negative Phase)であるとする。
(一)陽性相―疾病の軽快、神気爽快、食欲亢進、快眠、赤血球沈降速度増加、白血球増多を来し一般に治療成績良好なる感じを与へる。
(二)陰性相―全身倦怠、頭痛、筋肉痛、関節痛、食欲減退、不眠、嘔気、嘔吐を現はす現象で一般に症候の増悪を来すもので軽度、継続期間の短きを以つて可良とするものである。が、一、二時間より五、六時間に発し二十四時間に消退し、次に陽性転帰をとるのが普通であるのと、刺戟療法の教へるところであり、従つて
イ、適当刺戟は直ちに諸症の減退を見。
ロ、刺戟多きときは悪寒、戦慄をもつて高熱を発する。
ハ、最大刺戟は虚脱を起し、体温反つて下降することがある。
ニ、甚だしく過度ならざる刺戟であれば両日後に陽性相の現はるゝものである、従来存せし熱も下降するものである。
といふてゐるが、「続名家灸選」には「凡そ灸後寒熱、耳鳴、眩暈、頭疼、唇口乾燥し、痞満不食の証ありて、其の脉浮・滑・緩・洪ならば陽気通暢の象(即ち陽性相)であり、これは艾火活壮の効にして瞑眩であり、喜ぶべきものと為し、停止すること一、二日にして復多く灸す、若し其脉沈・緊・細・数・実・長・結・代ならば 火気炎逆の象(陰性相)で火邪に属するのだから施灸してはならぬ」旨を記してゐる。彼此参看すれば既に刺戟療法的理念のあつたことを知ることが出来るであらう。
最後に医師大久保適斎氏の長鍼運用の方法を述べてこの項を終わる。
(五)大久保適斎氏の鍼治論
今、心、肺二臓の手術を頚交感神経に取り、各種の内臓刺点を腰椎に求むる時は、其の神経経絡、彼れ是れ相混じて、各器各別に奏効すること能はざるに似たり、是身体組織に於ては各々撰択機能あるを以て其の憂を脱る、猶薬味の身体に於けるが如し、抑も薬味の身体中に入るや、血管水脉に輸入し、全身各所均一に循環するも、其特異性に従つて患部にのみ奏効す、鍼治の刺戟も亦然り、全神経の実質分子の配列(神経痛に於て、解剖的変化を見ざるものあり、又著しく解剖的変化あるも、神経痛を発せざる事あり、故に神経痛の原因は神経の分子変化なりと見倣す説当を得たりとす)病体変化を起し、例へぱ胃痛を発すれぱ、常に他の刺戟を待ちて常体に復せんと欲するの状あり、故に一の刺戟其の局所に対して転換作用を呈し、其の他健康の神経は、其刺戟を要せざるを以て、之に抵抗し、刺戟をして他に通過せしめて顧みざるに職由す、是即ち一の撰択機能に他ならず、今術者刺戟の際患者疾患ある局部のみ、軽微或は強大なる掣痛様に感を覚知するを以て証すべし。
而して頚部刺鍼刺入の寸法は、是を実地解剖に徴するに、第五頚椎と、結喉との周園に於て三十五センチの回りの存する人に当りては、第二位点に於て、直入関節突起に達するには四十センチ半を要し、鍼尖を僅かに外方に向けて進入して、横突起間、即ち頚神経前支の派出所に達するには六センチを要することを記憶して、手術に従事すべし、腹部内臓手術の三位点は、皆腰椎に於て、其の第一位点は、腰椎第一第二、或は第二第三の横突起間を目的とし、刺入すること、二寸乃至二寸五分、是れ大陽叢即ち内臓動脉軸叢及び大小内臓神経の支別に刺戟を伝搬するものにして、専ら胃肝の機能、(「マイヒルスト氏」曰く「肝に於て肝包の神経痛、及び灌漑性充血、代賞性充血、即ち反射的に血管運動神経に依るもの、又月経閉止に之を招き又月経閉期に達する婦人、若しくは子宮卵巣の疾患を憂ふる婦人に発し、或は常習失血の閉止に由て充血を発するものにあり、而して、肝充血の発生神経作用に重要の関係を有することを忘る可からず、例へば「フオンフレーリヒス氏」は動物に就き内臓神経節を切除するに由りて、充血を来すを見る、又「グラウデ・ベルナルト」氏は、神経中軸を刺戟するに由て、肝内の血量に変化を来すを見たり、故に充血を発するには神経力障碍に著しき関経を有するものならん、然れども身体の病理には、未だ其の機転を精検すること能はずと論ず。故に肝の充血に対し、刺戟其の病理に従つて、強弱軽重の刺鍼を謀り、益々研究すべし)及び尿の分泌を調理す、其の尿分泌の目的とするには、左側を要し、専ら胃の上に刺戟を与ふることを謀るべし、又腹の機能亢進し下痢あるものを鎮静す、 糞中の水は大抵百分中七十五%を佳とす、性酸性なり、而して糞便の厚薄は腹の蠕動に関し、其の機能亢進せば、腹内容物の通過疾速にして其液質吸収の暇なければ、水分増加して下瀉す、其の他神経切断に由り、或は他の事情に由り、腹神経及び淋巴管麻痺すれぱ下瀉す、此の時に当つては強直性刺戟を与ふべし、共の他、交感神経解剖上の関係、及び生理の詳細は、医師に質問すべし、之れ大小内臓神経の制止作用と、脈管収縮神経とを亢奮せしむるに由る。而して劇瀉の脈管及び尿崩の細尿管収縮を要するものは、持続性刺戟を行ふものとす、之に反して、「尋常下痢は 軽刺戟にして、専ら大小内臓神経、制止繊維を亢奮せしむるを可とす。
さて鍼の妊娠子宮に及ぼす影響について述べると、最も能く確実に効を奏するものぱ第三位点に如かず、然れども臨産或は子宮の収縮を要せんと欲せぱ、漢家の謂肩井、合谷 三陰交に於て鍼するも可なり、今生理に由て考ふるに子宮の運動を発せしむるもの数多あり、直接刺戟と反射とに由るものは、第一は下腹神経叢、第二は薦骨神経叢の機する所の勃起神経(「エツクハルト」氏の)第三腰部薦骨部の脊髄にして(其の体を刺戟すれば最も強き運動を発す、此刺点、神経衰弱に因する陰萎に効あるも暴与に依つて後害の患あるを以て、其の詳細を論せず)其の反射に由るものは、坐骨神経と、膊神経叢(膊神経叢の中心を刺戟すべし)なり又人類に於ては乳房を刺戟すれぱ子宮の牧縮を発せしむ、故に肩井は、其針尖の方向に左右すれぱ、膊神経叢の中心に触るゝ可く、三陰交も亦この鍼尖を左右せば坐骨神経の末端に触るゝを以て、其の収縮を起さしむべし、而して漢家、曽て此の二点を妊婦に禁ず、誠に故あり其反射的作用収縮軀胎の患を発するや、未だ知るべからず、故に今暫く其の説に従つて是を避くるを可とするも臨産の排出を助け、不規則の陣痛を除くは前論の如く、第三位を必要とす、既に胎児発育中止のものは、正規の排出力に強盛を増加して、速かに排出を遂げ、産婦に徒らに努力せしめ、疲労を増加せしむるなく、且つ刺戟そのものゝ為に脱胎早産せしむるに非らざる事は出産胎児の現状に従つて、自ら明瞭なり、故に懐妊中も、第三位の如きは、敢て恐るゝものに非ず、是畢竟該点は、子宮保護の効あるを以て、其の主意を心念に置き従事すべし、是れ恰も近時医学の進歩に従ひ産婦に麻酔法を施し、或は四%の「コカイン」水を陰唇子宮頚部に塗擦して疼痛を減じ、而して其の排出は、之れに反して十分の働きを為し得る者とし、且つ、「キーネル」氏は感伝電気を用ひ疼痛を緩解すると同時に、陣痛排出力を強大ならしむるの効を説けり、刺鍼は電気を用ゆる法より簡易にして一層の便益あるを以て刺鍼の臨産に有効なる所以なり」といふてゐる。又一第三位点に於いて直腸に作用せしめんには四寸刺入す、又刺点正点十一位、回気鍼(水溝、彧中、神蔵、内臓第一位点) 五位、膀胱一位(曲骨より下斜一寸五分乃至二寸五分)横膈膜鍼三位(頚、腰、章門)歯痛鍼二位(聴会、頬車)刺鍼とて相当深刺してゐるのであるが、これ等は標治的深刺の法を見ることが出来る。
(六)九鍼
以上の説論を眺めて、こゝに改めて霊枢、九鍼十二原篇の九鍼を想ひ出すのである。即ち
| 一、鑱鍼 ―― | 巾鍼に則る、末を去ること一寸半にして漸く鋭くし、長さ一寸六分、熱頭身にあるを主る、「古今医統」には箭頭鍼といふ。 |
| 二、圓鍼 ―― | 絮鍼に則る、其身を筩にして鋒を卵にして、長さ一寸六分肌肉を傷らず、分肉の間の気を治す。 |
| 三、鍉鍼 ―― | 黍粟の鋭なるに則る、長さ二寸半、脉を按じ、気を取り、補を用るに利あり、脉気虚少によろし。 |
| 四、鋒鍼 ―― | 絮鍼に則る、刃は三隅にして末を鋒にす、長さ一寸六分痼疾を発し、癰熱血を出すことを主る、所謂三稜鍼なり。 |
| 五、鈹鍼 ―― | 剱鋒に則る、広さ二分半長さ四寸、大癰より膿を出すことを主る、剱鍼ともいふ。 |
| 六、圓利鍼 ― | 釐鍼に則る、毛の如く其末微大にして反つて其身を小にす、長さ一寸六分深く内れて癰痺を取ることを主る。「古今医統」に曰く陰陽を調へ、暴痺を去り飛経走気に用ふ、員利鍼とも書く。 |
| 七、毫鍼 ―― | 毫毛に則る、形蚊虻の喙の如く長さ一寸六分、寒熱痛痺絡に下るを主る。 |
| 八、長鍼 ―― | 綦鍼に則る、鋒利くして身薄すく、長さ七寸深部遠痺を主る。環跳鍼ともいふ。 |
| 九、大鍼 ―― | 鋒鍼に則る、其鋒小し、円く尖ること挺の如く長さ四寸大気関節より出でざるを主る。燔鍼ともいひ長さ四寸風虚・腫毒・解肌排毒に用ふ。 |
とある。これを見るに、多くは外科的に用ひたるものゝやうであるが、毫鍼、員利鍼について は「鍼道発微」にもある通り、毫鍼は柔和に刺して補をめあてとし、員利鍼はいなづまの如く、花火の如く響かせ、気をして炮むのはつするかのごとくひゞきを総身に通ずるに用ひてゐるが、即ち瀉に用ひてゐる。
これ等は鍼の運用の進歩を物語るもので外科的物質的なるものより、生命生機の作用を目的とした微鍼に発展したことを示すものである。即ち、標治的なるものから、本治的なる「経絡治療」にと止揚されたのであつた。「証の科学」の素材として、現実に一つの体系を備へる約束が、とつくに、かくのごとく、つけられてゐたのである。
鍼灸術の本領はこゝに至つて全機的となり、綜合全体的治療の面目を具備するに至つたと見られると思ふ。
第十一節 治穴配合の方則及び臓腑取穴法
以上で我々は鍼灸の仕方を知つた。が、具体的な病人を前にして、如何に治療穴を選択し、如何やうな操作を与ふべきであるかについて考へねばならない、それには脉証によりて陰陽虚実臓腑を決定し、補瀉すれぱ足るのである。然らば如何なる方式に於いて治穴を決定するか、といふに上掲表の治穴配合の方則に従つて穴を決めるのである。又穴をとるには上掲「五行要穴」を知らねばならぬ、木火土金水にそれぞれ臓腑が配当されてゐる。臓は陰で、腑は陽である。各経各々に五行の性質を帯びた穴がある。従つて、各々はその性質を有してゐると解してよい。これを表にすれぱ次のやうになる、この表の穴を図式にしたのが、要穴図なのである。木生火、火生土、土生金、金生水、水生木が相生である(母子関係を示す)木尅土、土尅水、水尅火、火尅金、金尅木が相尅関係を示してゐる(相生と相尅から勝復関係が出て来る)
これ等木火土金水にそれぞれ臓腑を配当して、それを、脉証と合せれぱよいのである。そして治穴配合の方則にのつとつて、臓腑の虚実を弁ずれぱ後は所用の穴が出て来るのである。後は、補穴を補し、瀉穴を瀉せば治療は終るのである。
第七図表 五行要穴図
上図中央にあるのが正穴、母方にあるのが、母性穴、子方に有るのが、子性穴、尅線上で、勝つところにあるのが尅穴、不勝ところにあるのが畏穴、その周囲にある、原穴、郄穴、絡穴、募穴、兪穴を圏穴と称して置く。
第八図表 十二原穴、要穴、郄穴、絡穴、兪穴表
第九図表 治穴配合の方則
第十図表 臓腑虚実補穴瀉穴表(治穴配合の方則によつて取穴したもの)
第一公式正経自病の時は左表の外に自経圏穴を虚なら補、実なら瀉にとる又陰陽虚実あるとき、例、陰虚陽実のとき同一圏の陰穴を補ひ陽穴を瀉すべし。猶ほ虚の時は母性圏穴を補、実の時は子性圏穴を瀉す。
(1)要穴解(圏穴解)
五行要穴図にある圏穴はそれぞれ重要な意味を有するもので、次に略解を試みる。
イ、原穴
臍下腎間の動気は人の生命なり、十二経の根本なり、故に原と名づく、三焦は原気の別使、三気を通行す、五臓六腑を経歴し、原穴相応ずる。即ち、五臓六腑のどの病にも補瀉ともに使用する穴である。
ロ、郄穴
ゲキは隙である、気血の聚るところ、急病に応用する穴である。
ハ、絡穴
邪気侵入緩慢か、久病なれるものに使用する、慢性病に多く使ふ。
ニ、兪穴
輸であり、委輸である、経気これに由つて彼れに輸すといふ、陽にある、募と相交貫す、陰気発する所で陰病は陽に行く、だから陰病は陰より陽に引くに此穴を用ふ。
ホ、募穴
募は募結の募である、経気の聚る処である、募は陰にある陽気発する所、陽病は陰に行く、陽より陰に引く、兪穴と交相貫通す。
ヘ、八会穴
難経四十五難に「熱病内にあれぱ、其の会の気穴を取る」といふてゐるが、八会穴は府会(中脘)蔵会(章門)筋会(陽陵泉)髄会(絶骨)血会(膈兪)骨会(大杼)脈会(太淵)気会(膻中)をいふので、それぞれカツコ内の穴が会穴である。
ト、十五絡穴
鍼灸聚英に「実すれば身尽く痛み、虚すれば百節尽く縦む、実すれぱ絡穴を瀉し、虚すれぱ之を補ふ」とある、十五絡はこのやうな時に応用される。
十五絡穴は列欠(肺)、通里(心)、大鍾(腎)、内関(心包)、蠡溝(肝)、偏歴(大腸)、豊隆(胃)、支正(小腸)、飛揚(膀胱)、外関(三焦)、光明(胆)、尾翳(任脉)、長強(督脉)、大包或は虚里(脾の大絡)をいふ。
以上述べし外に足の太陰と任脉との交脈穴下脘、足の太陽と督脉との交脈穴百会、督脉と足の太陽との交脈穴風門、手足の三陽と督脉との交脈穴大椎、足三陰の交脈穴三陰交、足三陰と任脉との交会穴関元、足の陽明、手太陽、任脉との交会穴上院、足少陽と陽維との交会穴風池、足少陽ち帯脉との交会穴帯脉等凡そ七十餘穴は又疾病反応の著明にあらはるゝ穴所となす。
さてこの他に鍼道発微の要穴、鍼灸茗話の二儀(不容、太乙)三二台(中脘及その両傍)四霊(臍の上下左右一寸五分)、四柱(肓門、帯脉)、五柱(風府、風池、天牖)、星文(天窌、肩外、天宗、大椎、肩井、臑兪)、その他三臑(五里、消濼、臂臑)、三肘(少海、曲池、尺沢)、五臂(三里、温溜、支正、内関、外関)、三腕(陽溪、陽谷、太陵)、三掌(魚際、労宮、合谷)、三関(梁丘、陽陵泉、陰陵泉)、五脛(三里、絶骨、承山、飛揚、三陰交)、三足(然谷、太衝、申脉)等はほとんど多く上述正典上の穴を選んだものであることはその内容を一見して知ることが出来る。
その他近年発見せられたと考へてゐる私方穴も又上述正典の穴の移動せし所を指示したやうなものゝ多きは仔細に之を点検すれぱ自明のものが少くないのである。
従つて吾人は正典の穴を研究し然る後に変法たる私方穴の研究に及ぷべきものと思惟するものである。何故ならば暗中模索迂遠に堕し、正道を失するを惧るゝが為めである。
第十ニ節 鍼灸技術の稽古
鍼は一本の針金であり、灸は艾を燃焼させるだけである。 至極簡単な治療法である、だから原始的な治療法だなんて云はれるのである、簡単であるからキキメがないといふ人があつたら、それは誤りである。和田東郭先生は「用法簡者、共術日精、用方繁者、其術日粗、以簡為粗以繁為精哀矣哉」といふてゐる、名言である。我々の使用する鍼は極めて簡である。これを以つて、凡ての病に応用して病を治そうとするのだから、その用は繁とならねばならず、手技が精とならねばならぬ訳である。灸にしてもその通りである。こゝに先哲は技術の稽古になみなみならぬ修練を積んだものであつた。
熊本の鍼医太田隣斉先生は一本鍼で鳴した、チョンまげ姿に大刀を帯びて諸国を鍼の修業に歩るいている写真を見たが 一本の鍼を扱ふに、昔しの鍼医は十数年を修業にかけたものであつた。これは水府の西村流、千葉の八木下先生、東京の吉田弘道先生等皆然りであつた。
太田隣斉先生の唯一の門人、尾田喜八氏が今でも熊本にをられるが、氏のお話では隣斉先生に入門し、三ケ年は座敷に入れられず、座敷の廊下に坐して、掌による(1)舟揉み、(2)腕によるあともみ、(3)両手によるもみわけ、(4)腹部のもみあげの稽古に一年位、後、管弾き、管捌き、片手取りを三年、綿枕への刺鍼が三ケ年、終つて銅人形へ十四経絡の経絡線を引き、大体の練習が終り、坐敷に入室を許されるのであつたといふ。 「要は稽古である、術を練ることである、腕が大切だ。病人が痛むといふても、こつちの見つけるところと違ふ、こつちの見るところが本当だ、病人のいふ通りにやるのではいかん、鍼は経をたどり経の感ずるところに刺すが鍼の道だ」と尾田喜八氏は言はれた。最近の治験に根治法として開腹手術をせねばならぬといふ右側卵巣嚢腫を所謂一本鍼で刺し、十分間位刺して治した。先づ気を伸べつらし、腫物(硬かつたら受合はぬといふ)の周囲に鍼尖を達せしめ、刺鍼転向の心持ちで四方にむけて刺す。それが終つたら、側臥させて腰へ引鍼するのである。帯脉、京門等にも刺すのである。熊本県立病院で肘関節炎でギプスをかけてゐたものを肩髃の鍼に一本鍼的に鍼し、後は脉による本治法で治したといつてゐた、全快してギプスが不要になつたので、尾田氏のもとに置いてあつた。かやうに鍼は簡なれど術精なれば不思義なる現実をあらはすことが出来るのである。
昔は硬物通し、浮物通し、生物通しの練習をしたものであつた。
(一)硬物通し
硬物通しとは桐、杉、樫の木の順序に初めは五厘位にしてこれに二番位の鍼で撚り通し、
に次に一分二分三分と漸次厚くし五分1寸に至つた、桐が済めぱ杉、杉板が済めば樫といふ風 堅木の稽古に及んだのである「雨滴穿石」といふことがある。ついにご盤に刺し火鉢をさへ刺通したと云はれてゐる。
その撚る心は杉山和一先生の云はるゝやうに「蓮の糸を以つて鉄石を穿つが如く撚抜く」のであつた。これが済めぱ浮物通しである。
(二)浮物通し
盤中に水を満たしめ果物を浮めこれに刺すのである。盤中の水外に出ても不可だし、果物沈みてもダメだといふ、ところが仲々刺さらないものである、重心をみつけても、今度は刺入が思ふやうに行かない、この稽古も一通りではない。
(三)生物通し
浮物通しが経ると犬、猫に刺す、「睡猫に刺して覚醒せざる」をもつて上手となすのである。秋山流では三味線の糸をスポンジに通して、之に刺鍼し三味線の糸を刺し通すに至れば印可が下りたといふ。
(四)生体に於ける硬物通し
何故に古人はこのやうな稽古をしたかといふに堅硬岩鉄の如き身体のものあり、病みてこるものあり、或は骨の如く硬きものあり、又は肋軟骨、恥骨軟骨の如きものを刺通す必要がある。かゝるとき「腕前」が出来てゐねぱそれ等の患者を到底扱へるものではない。この為めの稽古であつた。
(五)生体に於ける浮物通し
浮物通しは生活体の精微に対し過誤なからしめん為であつた。喘息に扶突穴、天突穴、上肢肩背胸中の病に欠盆穴に刺すに当り、貴要臓器を内含する所であるから釐毫の差もあつてはならぬ、浮果の浮動する獲へ難きに似てゐる。気を得て補瀉する刺鍼にありてはかゝる練習を望まれたるは当然であつたらう。
毛物とて生物である。生活体として人間に近い、気の往去を鍼下に知るは先づ、毛物を扱 ふが順序である。
(六)気の往来
気の往来とは「鍼道発微」に「気のいたる事動脉のかたちの如く、又釣針へ魚のかゝるが如く、意をもつて是をうかがひ遠くめぐらす時はたとへば腰へ立てたる鍼手足へひびく、其のかたちいなづまの如く花火のごとし、又久しくとどめて進退するときは其の気の往来すること炮玉の発するがごとし、其のひゞき総身に通ず、其術誠に妙なり、かゝるが故に邪を瀉し精をとゝのふること自在を得ぺし」といふてゐる通り。
鍼灸要法指南に「鍼の枢要とするところ気也、気は正気なり、意を密かにして鍼尖を候ふに冥々として其形知がたし、たとへば魚の鉤を呑んで浮沈動揺するが如く鍼尖動き渋る是を気の来るといふ。気至れば鍼を留ることなかれ、真気脱する故也、気の来らずと云ふは豆腐に刺が如くにして力なし、鍼尖を動揺し弾振すれば気至る也、是を催気といふ」とある。
気の往来は(1)沈緊を覚え、(2)動気す、(3)動揺する、(4)浮動する、(5)沈渋する、(6)重温を覚ゆ、(7)覚熟、(8)覚清涼、(9)鍼自動等で表現されてゐる。
かやうなる気の往来を押手、刺手にて知るに至れば一人前の鍼医といふことが出来る。
この稽古中常に気構へ心構へ体作りをやかましくいふ、気海丹田に力を入れ、禅室に入るの気持ちで、半眼以つて暮夕を考へず、ひたすら鍼に全精神をつけるのである。蚊でさへ、将に刺さんとするとき体作りをし、足をふん張り、垂直に針を皮膚に立て、徐々に挿入するではないか、霊枢終始篇に「鍼を刺す時は視ることなく、聴くことなく、言ふ事なく、働くことなく、只意を密かにして鍼尖に心をつけ気の去来を候ふべし」とある。これ等自然の妙理に直参せずして理を論ずればとて詮ないことである。
内経に「薄氷を履むが如く」「手に湯を捜るが如く」「手に虎を握るが如く」とある、鍼を持て剛弱を示すものにして、「極めて堅く敢へてゆるさざるを佳とする、堅ければ病に中る事疾し、但偏えに堅きを佳とするに非ず、忽がせにすべからず」(鍼灸要法)といふてゐる言葉は味ふべき言である。
鍼は心である、深く慮んぱかるべきである。一本の鍼にて万病の錠前を開く、技に於いて精巧ならざるを得ないのは当然である。
(七)浮水六法
管鍼法に於ける弾入もその通りである、浮水六法といふて遅、緩、数の三法に軽重(陰陽)が入り六法となるのである。
(1)軽遅は鍼を陽に軽く四つ打つて弾入する。
(2)重遅は陰に重く四つ打つて弾入する。
(3)軽緩は陽に軽く五つ打つて弾入する。
(4)重緩は陰に軽く五つ打つて弾入する。
(5)軽数は陽に軽く六つ打つて弾入する。
(6)重数は陰に重く六つ打つて弾き入れるのである。 これは「杉山真伝流」の弾入であるが、普通はトン、トン、トン、トトン、トン、と初めは陽に打つて、後に陰に打つのである。
太田流の弾入は陽打六辺、陰打三辺に入れる。
又片手管捌きは片手挿管法で要領は鍼管に鍼柄頭をひつかけ、鍼柄の重さで管中にすべり込ませ平らにして鍼柄を拇指と示指で撮むのである。それも稽古すればたやすく出来るものである。要は術を練れば出来るのである。弾入の叩き方は鍼柄頭に垂直に当るやうに、鍼体の弾力より弱い力で加ふべきである。(垂直に鍼柄頭に当るやうにすれば線香でも鍼は刺入出来るものだ)かくして、
(1)弾入無痛。
(2)刺入無痛。
(3)抜去に無痛。
(4)鍼曲らず。
(5)刺抜の時間早きを上手と為すのである。これに実地では気の往来がわかれば上工とされるのである。
(八)灸の稽古
灸にしてもその通りである。ただ艾を撮んで皮慮につければよいといふものではない。糸状艾炷、半米粒大、米粒大、小豆大、大豆大等の艾炷を均等の大さに撮む練習をせねぱならぬ、艾炷の作り方は(1)同じ高さ、(2)同じ直径、(3)同じ重量、(4)同じ硬度、(5)同じ底面を持つ円柱状又はピラミツト状の艾炷を出来るだけ早く作る稽古をせねぱならぬ、練習には早いほどよい、板とかビンとかに着けるのである。米粒大で一分間に三十個位着けぱ先づ一人前である。板やビンにつけるには塩水又は消毒液を浸した海綿か海綿様のゴムに指頭をつけ、この液を施灸点につけて、それに艾をくつつけるのである。
線香で火を移すにも又コツがある。灰のついてゐる線香で火をつけやうとすれぱ艾を釣り上げる、だから、灰をよくとつて、艾頭に火をつける際、線香をちよつと廻すやうにすれば、ころばすことも、釣り上げることも少ないものである。これも練習である。
かやうに、あらかじめ練習して病人に臨めば憶することなく手術が出来るものである。
かくして技術手い入れぱ石坂宗哲ではないが、「死物たる針を活物に応用」出来ることになるのである、こゝで針金に過ぎない一本の鍼が万病に対して、万薬のはたらきをすることが出来るから、万病に応用して、その病を治すこをが出来る訳なのである。
天源に出でたる天恵の術たるを、鍼に於いて我々はこゝではつきりと認め確め得るであらう。
第十三節 補瀉の方法
私は思ふてゐる、鍼灸は補瀉の術である。補瀉は鍼灸なる簡単な道具を精巧にする操作である。補は与へる、益す、加へる、救ふ、済ふ、実せしむ、興起生長さすとふことである。
瀉は取る、奪ふ、減する、尅す、抑へる、殺す、減衰収蔵さすことである。
湯液の汗吐下は瀉に属し、和養は補に属す、瀉は虚せしむることであり、補は実せしむることである。現代医学の強心剤投薬、滋血薬、栄養剤、興奮薬は補、瀉血切開切除、内臓外科は瀉であると見ることも出来る。補瀉は結局加減である。
(一)補の意味
補は細胞組織の生命力の積極的自我顕現化を目的とした手技であり、正気(生活体伸張の源泉、エネルギー)を興起生長さすことである。正気の補益充実である。
(二)瀉の意味
瀉は細胞組織の生命力自我顕現化遂行の障碍となる機構解消作用を目的とした手技である邪気(瘀血、悪血液、自家中毒、異物欝積、旺気)の勢力を減衰収蔵せしめることである。邪気を排除することである。
かくして、人間の全生機を振起し、原気を興起し、病的なるものを減衰し、健康体たらしむるが目的なのである。
鍼下熱を覚えるは気の実であり補となる、鍼下清涼を覚えるのは気の虚であり瀉となる。
これは理論だけの問題ではない、実際両腕のうち一腕に鍼し、他腕に鍼しないで掌中の発汗の有無を見れぱすぐ実験出来る、鍼刺した方の掌は汗ばみ、刺さぬ掌は汗ばまぬ。
婦人腰脚の冷えるもので、腎虚証に際し腎の補である、復溜穴(金性穴)に鍼を補に立て、気来らざれば、催気し、気来れぱ押手刺手を離して見る。初めうごかなかつた鍼がビンビンと自動するを見る、ビンビンとうごけば、六部定位の脉の虚がとれて来る、病人は腰脚の温かとなつたと云ふであらう、ちつとも不思議なことではない、実験してみれば分ることである。
補は加へることである、不及、不足、虚を対象とするからである。
瀉は減らすことである、有餘、緊堅実を対象とするからである。
加へるには、加はるものゝ容る余地がなくてはならぬ、一杯入つてゐるところには入りやうがない。従つて、虚の状態にして置いて入れる方が理論にかなふ。息を吸ひ込めば力が入る、充実する、息を出せば力が抜ける虚弱となる、手足を緊張させれば力が入る、手足をダラリとさせれば力が抜ける。従つて、補には息を呼させ、力を抜かせて不足、虚の有り様にして刺すが、理にかなふ。
瀉は息を吸はせ、四肢に力を入れさせて有餘充実の状態にして鍼刺するのが理の当然である。
鍼を皮膚に突き刺すことは一つの傷病である。微かなりとも、やゝ大なりとも、傷病には変りない、生きものだから、切れぱ血が出る、穴をあければ体液の出るのはいふまでもない。泄すが瀉である、淋巴液や血の出たのをそのまゝにして置くのが減になる、瀉になる、従つて鍼痕を閉ぢてはならぬ訳である。この反対の理念である補には手つとり早く閉ぢねばならぬ。こゝに、開闔の補瀉の法ありと説くは不思義ではない。三稜鍼、鈹鍼、鑱鍼は大瀉の鍼であり毫鍼は補鍼であることも分明であらう、太鍼が瀉になり、微鍼が補になる、それもあたりまへである。同一の太さの鍼を使ふ場合、鍼口を大きくして泄れ易しくするのが瀉となり、泄らさざるやうにして、内に気を集めるのが補になるのも当然、こゝに揺動の補瀉が立てられた訳である。
形気の虚。羸気弱癢麻は元気がないからである。これを補ふは当然、豊肥堅硬疼痛は充実でこれを瀉するは当然である。
老人貴人は形気弱きが故に補意に、壮人賎者は形気充実するが故に瀉意に立てるが当然である。
陽分は瀉すること多く、陰分は補すること多い。が、陽中の陰は先づ補し後に瀉す(金鍼賦八法論に曰く)陰中の陽は先づ瀉し後に補すの概念の出るも発展的手法の至るところである。(金鍼賦八法論に曰く)
併しながら、補といふも、瀉といふも相手のあることである。一杯の酒でも真に酔つぱらう者があると思へば、一升瓶を二三本もひつころがして猶ほ平然たる酒豪家がゐる。一、二合で丁度よい人もゐる、補瀉もその通りである。薬剤の量と同じだ、従つて、「蔵珍要編」には援補、 緩引補、留補、極補、徐補、急瀉、暫瀉、漸瀉、浅撚補瀉、深撚補瀉が出来たのは理の当然である、温鍼とて鍼を口中に温めて刺すとか鍼柄に施灸すれぱ補となる、身体に合ふからである。含まぎるものは劇しくあたる瀉となるのである。(これ等の詳細は別著に譲る)
鍼を体中に永く入れて置くと補となる、体中にあまり永く留めないと瀉となる、昔は補に「五常上真六甲玄霊気付至陰百邪閉理」と三扁念じ、瀉に「帝扶天形護命成霊」と三扁踊するといふ。鍼医の神気を鎮めるといふぱかりではない、異物としての鍼が体中に入れぱ生活体は先づ排除融化現象を起す。猶ほ留まれぱ、被包現象を起す為めの細胞がその部に集るといふ、これは東大教授緒方、三田村両博士の実験的研究報告である。呪文のよつて来る実相が明白になつたやうな気がするではないか、次に補瀉の一般手法をのべやう。
補は用鍼を温める、経絡に従つて指腹でよくなでる、穴を厭按する、爪を以つて穴処を押へる、気の来るを候ふ、経に従ふて鍼を随にふせて、呼に従つて刺す、気得るまで刺入する、気来らざれば催気の法を行ふ、補し終つたら、吸に従つて徐々に抜き上げ、抜除せぱ直ちに鍼痕を 操み閉ぢるのである。この際(刺入の間)五常云々の呪文を誦す、瀉は用鍼を温めない。経に逆になでる、穴を厭按し、爪を以つて押へる、気の来るを候ふ、経に迎つて鍼を伏せて、吸に従つて刺入す、気の催すを候ふ、気来らぱ患人をして呼さしめ、呼に従つて抜く、鍼痕を成るべく開くやうにし、鍼痕を閉ぢない、邪気をもらすのである。刺抜の間帝扶云々その呪文を諦するのである。
此間、脉を按じ、虚及び実が平となれば補瀉適正に行はれてゐる証拠なのである。
最後に広狭鍼灸神倶集「正邪相争ふの時に当つて針肌間の中に入つて宗気に触るゝときは宗気いよいよこゝに聚り憤激して力を出し、これを防ぐ故に邪気遂に敗走するなり、然らぱ微鍼の功は直ちに、これが邪気駆逐して去らしむるものに非ず、宗気の激発して針下に聚め、それが力増して邪気を駆逐せしむれば宗気の為には援兵加勢ともいふべきなり」を紹介して諸士の味読に供そう、鍼とは実にかくの如きものである。
次に灸であるが、要するに、温々冬日たる気持よき灸熱を感ぜしめるが補、猛烈夏日を思はせるやうな激烈なる灸熱を感ぜしむるが瀉となる。多穴は少穴に比して瀉、少壮は多壮よりも補、一穴を以つていへば、小艾炷小壮は 補、大艾炷多壮は瀉となる、これ等は組合せて、病人と病証と病勢によつて決めべきである。次に鍼灸の補瀉を表示する。
| 鍼補瀉 | 補 | 瀉 |
|---|---|---|
| 陰陽 | 陰病は補 | 陽病は瀉す |
| 呼吸 | 呼息に刺入し吸息に抜く | 吸息に刺し、呼息に抜く |
| 鍼尖 | 鍼を温めて用ゆ | 鍼を温めずに用ゆ |
| 提按 | 穴所を爪で強く押へて刺入す | 穴を強圧せず |
| 開闔 | 抜鍼後直ちに鍼痕をよく閉ずる | 閉ぢずそのまゝにして置く |
| 迎随 | 経に従つて斜鍼す | 経に逆つて斜鍼す |
| 用捨 | 無痛なるやう刺鍼 | 多少痛みてよし |
| 出内 | 徐刺徐抜正気を集める | 速刺速抜邪気をもらす |
| 過不及 | 病人の気根により弱きに弱く用ゆ | 強きに強く用ゆ |
| 弾爪 | 穴処を爪で弾き気血を呼びて刺す | そのまゝ刺す |
| 揺動 | 刺入せる鍼を震はせて催気す | 動揺大いにし穴を大にし邪気をもらす |
| 子母 | 虚せる経の母を補ふ | 実する経の子を瀉す |
| 虚実 | 麻痺、痒は虚なりこれに用ふ、按へて気持よきは虚なり | 痛腫は実なりこれに用ふ、按へて痛むは実なり |
| 方円 | 円は補なり、移なり、宣なり、補気なり(子母の補瀉の意味もある) | 方は迎へなり、盛気を瀉すなり |
| 寒熱 | 寒は補す | 熱は発散、瀉す |
| 浅深 | 浅く | 深く |
| 太細 | 細く | 太く |
| 補 | 瀉 | |
|---|---|---|
| 灸補瀉 | 点火燃焼自然たらしむ温々冬日の如き熱感を与へるやうにする。 良質の艾、柔かに撮み、皮膚に軽くつけ、乾燥せしむ燃焼した灰の上から施灸続行。 小炷、炷を高く底面を狭くす。 | 点火燃焼まさに皮膚に達せん時風を送り早く焼失せしむ。 猛烈夏日を思はすやうに劇しい熱感を与へるやうにする。 良質でなくてよし硬く艾を撮む 皮膚に密着するやうに貼ずる、燃焼した灰を一々除いて施灸する。 太炷、炷のたけ低く、底面を広く施灸。 |
第十四節 鍼灸科学の業蹟
明治の末期から鍼灸に関心を持つてゐた医学者が現代基礎医学的に研究してくれた。その研究論文、並に文献は巻末にある、その研究業蹟は大体次のやうに分けることが出来る。
(一)穴に関するもの
これは後藤道雄博士のヘツド氏帯と鍼灸術の研究並に京都医大生理学教室を主とする。即ち、石川日出鶴丸博士の交感神経二重支配法則に基づく学説、及び九大の小野寺直助博士の「圧診法」に於ける深部知覚点位ひである。後藤博土に従へぱ経穴はヘツド氏帯最高知覚過敏点だから、皮膚を灼かなくてもよい、温灸で事足りといふ、これは第二の血清血液に及ぼす灸の科学的業蹟と喰ひ違ふし、小野寺博士の説とも喰ひ違ふ、我々の臨床とはあまり縁がない。とかく、今までの科学とはこんなものである。
石川学説を主流とする学説は、まだ、治療の実際に役立つやうには組立てられてゐないといふ、ありそうなことである。だが、我々はその大成を渇望する、科学的な経穴が内臓に連り、或る病証をピタリと治する具体的な点を科学的に現実の病人に求め得る方法を教へてもらひたいものである。ことのついでに、科学的な器械でも出来たら結構この上もない。坊間にある「探索器」なんてものでなしに、真に臨床に使へるものをと我々は熱望する、何んでも科学で出来る筈なんだから出来ない筈がないと思ふが、だが、我々は我々の指端を練磨することにより古人の遺業を具現すべく努め、また実現しているのである。
(二)鍼灸を刺戟とし、血液像に及ぼす作用に関するもの
藤井秀二博士の「小児鍼」の研究は御苦労なものであつた。原志免太郎博士、青地正皓博士、 時枝薫博士等の研究も労作である。鍼は器械的刺戟灸は温熱的刺戟であり、変性蛋白体刺戟であると片附けてゐる、その通りである。然し、それが鍼灸の全部ではない。小児鍼と他の器械的尖鋭物との実験的比較が実験されなければ、またされたならば、小児鍼の研究も影を薄めはしまいが、小児鍼はたしかに交感神経緊張を招来し、網状織内皮細胞系をして作用旺盛ならしめ種々なる血液血清像に人体有益なる物質が増加するだらう、だから藤井博士の云ふやうに、Unstemmungstherapie 変調療法には相違なからう、が、尖鋭物質をもつて皮膚に接触的刺戟を与へても同様な結果が実験的現象として出て来はしまいか、出て来そうである。出るとすれぱ、藤井博士の研究は小児鍼の研究ではなく物質的尖鋭物の皮膚接触的刺戟の研究になるのではあるまいか、原博士以下の業蹟もその通りである。灸が単なる蛋白体刺戟療法ならぱ、原博士の云ふ通り、腰部八点穴でことたりる訳だ、腰部八点穴なんて名前をつけるにも及ぱない、皮膚のどこでもよい、いな灸するに及ぱない、京城大学の大澤健博士ではないが、Omuuine のやうな、Moxolのやうな蛋白体、血清を注射すればよい訳だ従つて鍼灸家なんて不要な訳だ、ところが我々鍼灸家は、そんな説には納得出来ない。何故ならぱ、鍼灸は現代医学とは別個な治療体系に基づいて治療してゐるからなんである。山崎順博士の言葉をかりて云へぱ、「今の幼稚な科学では分らぬ、明日の科学に根ざしてゐる」からなのである。
詳細は各論文について見られゝば分るが、こんなところに今の鍼灸の科学が位置してゐるのである。我々の臨床とはさして関係もなく。
第十五節 鍼灸科学化の方途
鍼灸術は科学的実践であると我々は信じてゐる、板倉武博士のいふやうに、従来の鍼灸科学は「病の科学」であつた。静態基礎医学的研究であつた。が、それでは鍼灸の本質的なるものはつかめはしないし、鍼灸の治療には役立たない。
鍼灸のあらゆる現象をそのまゝに「証の科学」我々のいふ「動態基礎医学」としてこそ鍼灸の本質的なものがつかめる、鍼灸は経絡を基調にする随証療法といふことに価値があるのである。こゝにこれからの鍼灸人のやらねぱならぬ重点がある。
鍼灸と人体との間に起る種々なる現象を私は「鍼灸現象」と称してゐる、この現象を人間に於いて、そのありのまゝにながめ、その自然現象から自然の理法を掴み取り、これに科学体系を与へるのがこれからの鍼灸の科学化なのである。
この為には、価値ある鍼灸現象をかゝる立場を取る科学者に提供しなければならない、この仕事を果すか否かは我々鍼灸人の双肩にかゝつてゐる、下手糞な鍼灸家の現はす「鍼灸現象」は価値少き素材でしかない、上手な鍼灸家の現はす「鍼灸現象」は価値のあるものであるに相違ない。こゝに我々は技術の上達を念願し、腕を練らねばならぬ一大覚悟をせねばならないのである。
この本を手にせる諸賢よ我々の技術を磨き上工の域に達することは患者が多くなると同時に、鍼灸科学化への礎石となることを忘れてはならぬ。
茲に鍼灸医術の門に入る必要があるのである、門は門である、何分その堂奥を究めんとする熱情をさまさざらんことを、鍼灸の科学化の為に、昭和鍼灸医学の為に熱願したい。
第十六節 結語
私は「鍼灸古典手引」を執筆し、鍼灸の本質的なるものを闡明し、明治以降の刺戟偏重主義、経絡経穴無用論者に対して我々の経絡治療を闡明しやうと企図してゐた、が、仲々その機会が得られなかつた。然も「医道の日本」はいち早くも「古典鍼灸手引」の広告まで出した、その手前もあり、著者たる私は困つたものだと思つた、が、一度はやらねばならぬ仕事である、ぽつぽつと原稿の原稿を整理して置いた。去る三月、九州一円並に中国大阪方面に於いて真摯なる鍼灸人と相語る機会に恵まれた。そして、経絡治療なるものをどうしても世に問はなくてはならぬとの志を堅くした。こゝに早急に稿をすゝめ「鍛灸医術の門」が出来上つた訳である。
門はどこまでも門である。門から玄関に入り座敷に上り、堂奥に至つてもらいたい。そして立派な臨床家になつてもらいたい。玄関から家屋の大要は近き将来やがて稿を改めて読諸子にまみえることを約束して置きたい。
過去数千年その道統を今に及んだ東洋医術は臨床の医学であつた。如何に病気を治そうかとの血の滲み出る古先賢の苦業の結晶であつた。こゝに独自の医学体系が樹立されたのである。
病気の観察と自然科学的知識の組織を目的とする西洋医学とはおよそ信念が異るのである。
治せばよいのだ。これが我々の天職なのだ、治す為めの学問、治す為めの修錬、治す為めの苦業、我々はよろこびをもつてやりとげやうではないか。
その為めには斯の門を入り、その堂奥にある汗牛充棟もただならぬ、東洋医籍の真髄と不易の真理を逞しき意欲を熱火と燃して、いどみ取らうではないか。
この気持で私はこの門を閉ぢる。
底本:『鍼灸醫術の門』医道の日本社 昭和23年4月25日発行